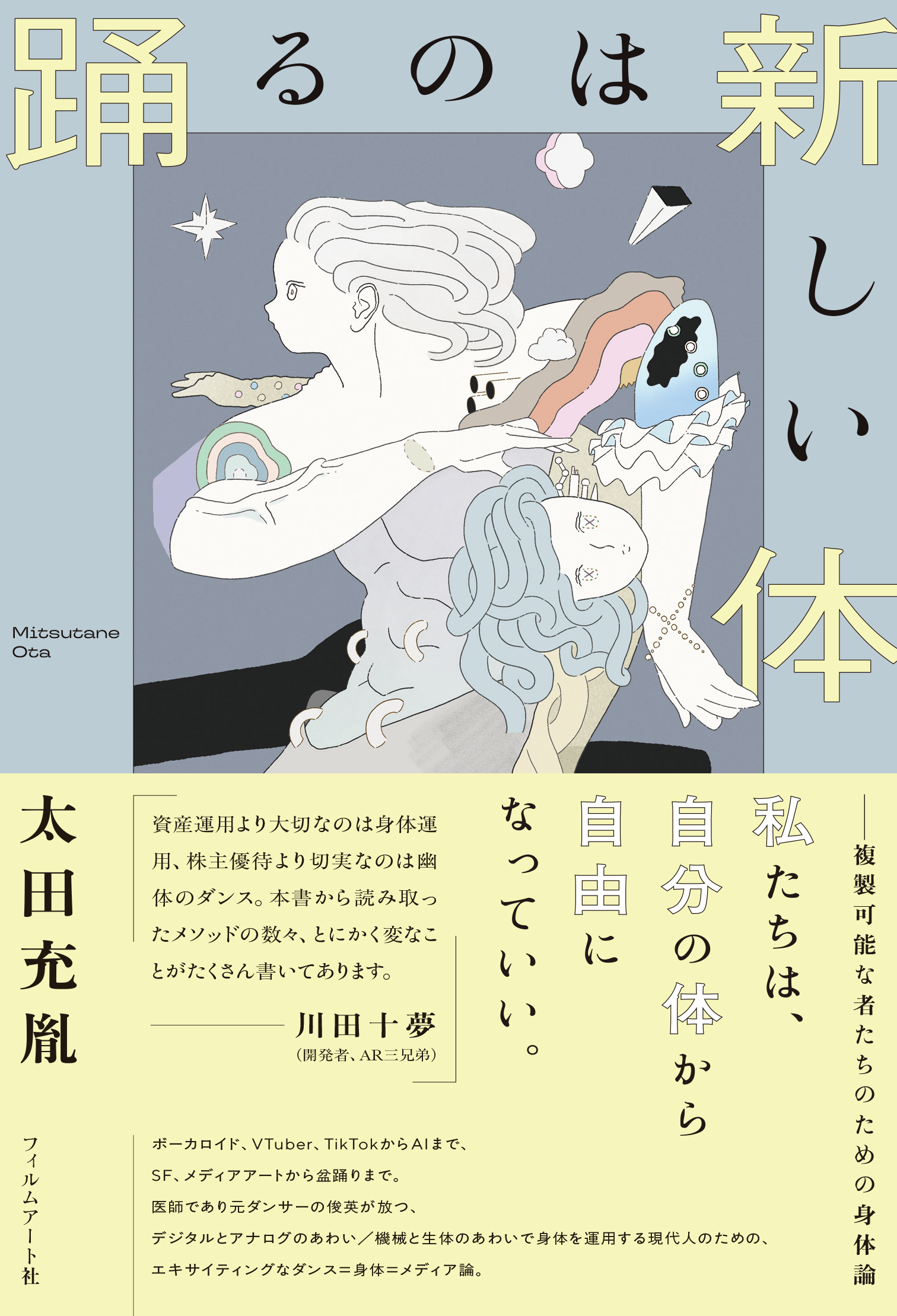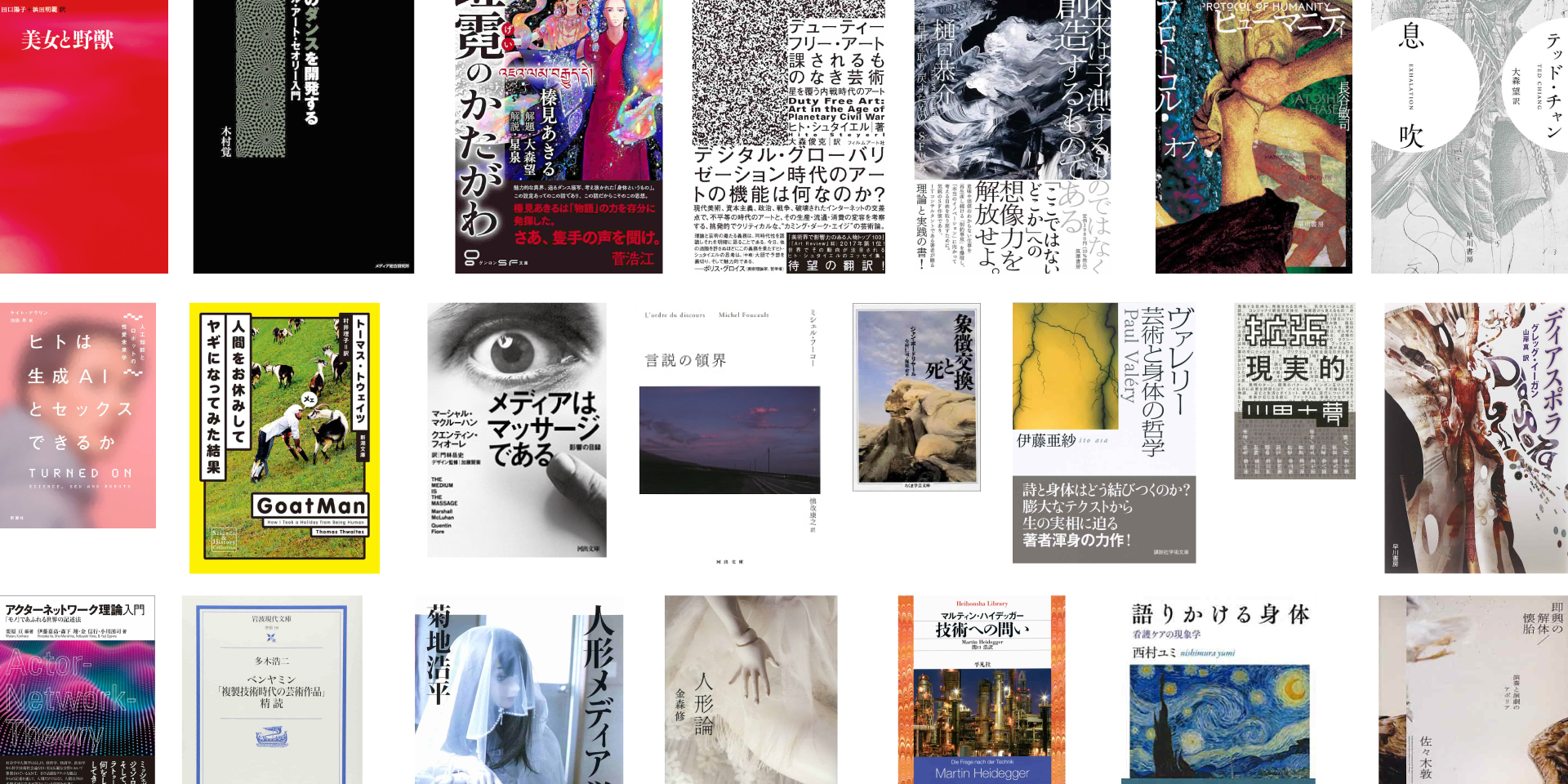
はじめまして、このたび『踊るのは新しい体』を刊行しました太田充胤です。ふだんは医師として診療をするかたわら、大学院の博士課程で科学史・医学史の研究をしたり、身体芸術を中心とした批評を書いたりしています。『踊るのは新しい体』では「新しい身体論」と称して、ヒトとモノとの境目がどんどん曖昧になっていく今日の身体を、ダンスを切り口として論じてきました。今回の選書フェアでは本書のテーマにちなみ、技術・芸術・身体の三領域にまたがって、関連する本や思考の源泉になった本をご紹介いたします。複製技術が芸術にもたらした変化についての古典的考察から、ヒト型のモノ、デジタル時代の身体表象まで。デジタルとアナログが混ざり合い、機械と生体が混ざり合う今日、みなさまが身体の未来を想像/創造する一助になれば幸いです。
選書・文 太田充胤
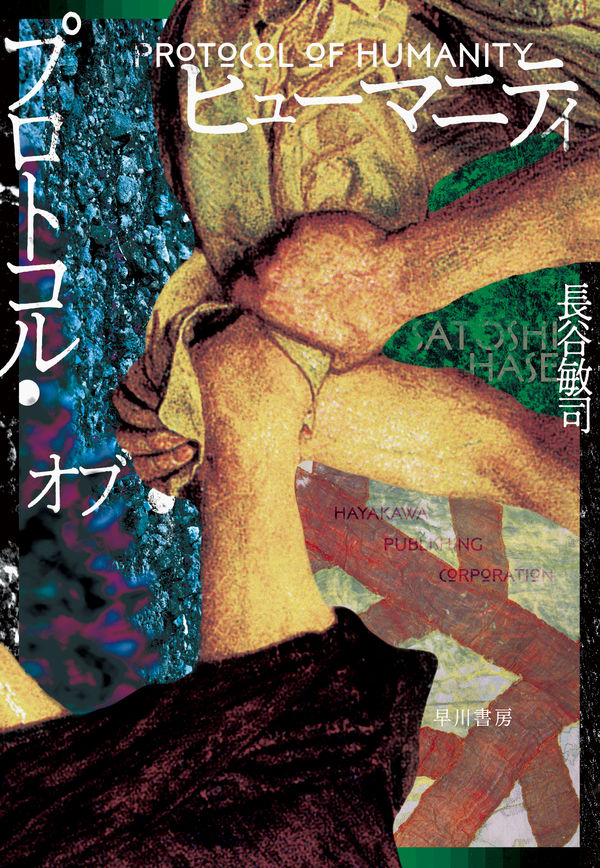
片脚を失ったダンサーが、AI内臓の義肢とともに再起を図るさまを描いた長編SF。奇しくも時を同じくして、ダンスの師だった父親が認知症を患い、日ごとに衰えていく。どちらの相手についても、ダンサーに残された希望はダンスを通じた対話だけ──。セッションを通じて浮かび上がる機械の人間性と、変容していく人間の人間性。ふたつの出来事を貫く、人間性とは何か、ダンスとは何かという問い。もう少し早く出ていたら拙著でも取り上げていたであろう大傑作です。
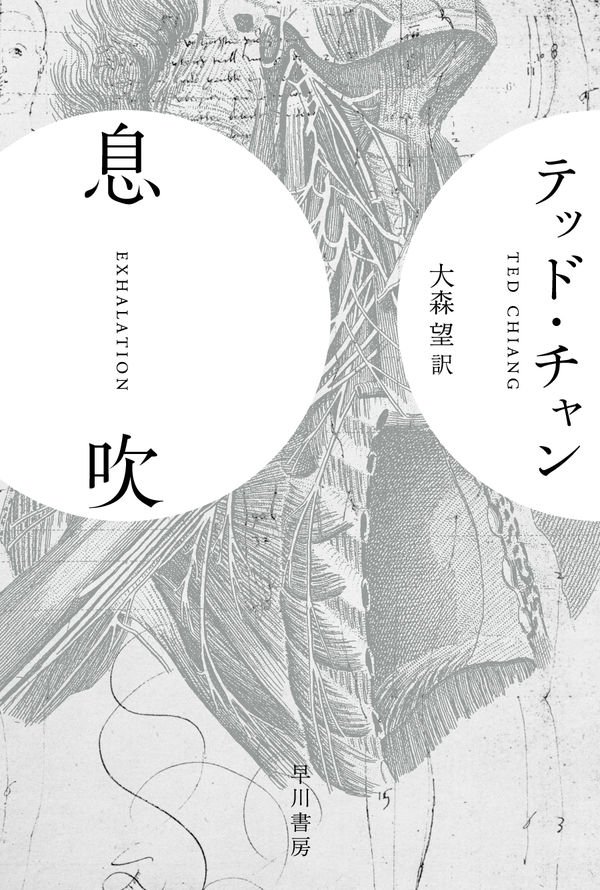
拙著でも扱った中編「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」は、仮想空間の人工生命が現実社会でどのような立場に置かれるかを描いた傑作。ほか、どの収録作もSFでありながら不思議と現実的な味わいがあります。イスラム世界の時間旅行、機械生命体の自己解剖、異種との意思疎通、考古学による神の存在証明、可能世界と自由意志……モチーフを並べるだけでも垂涎ものの、SF全部乗せフルコース。巻末の著者解題も必読です。
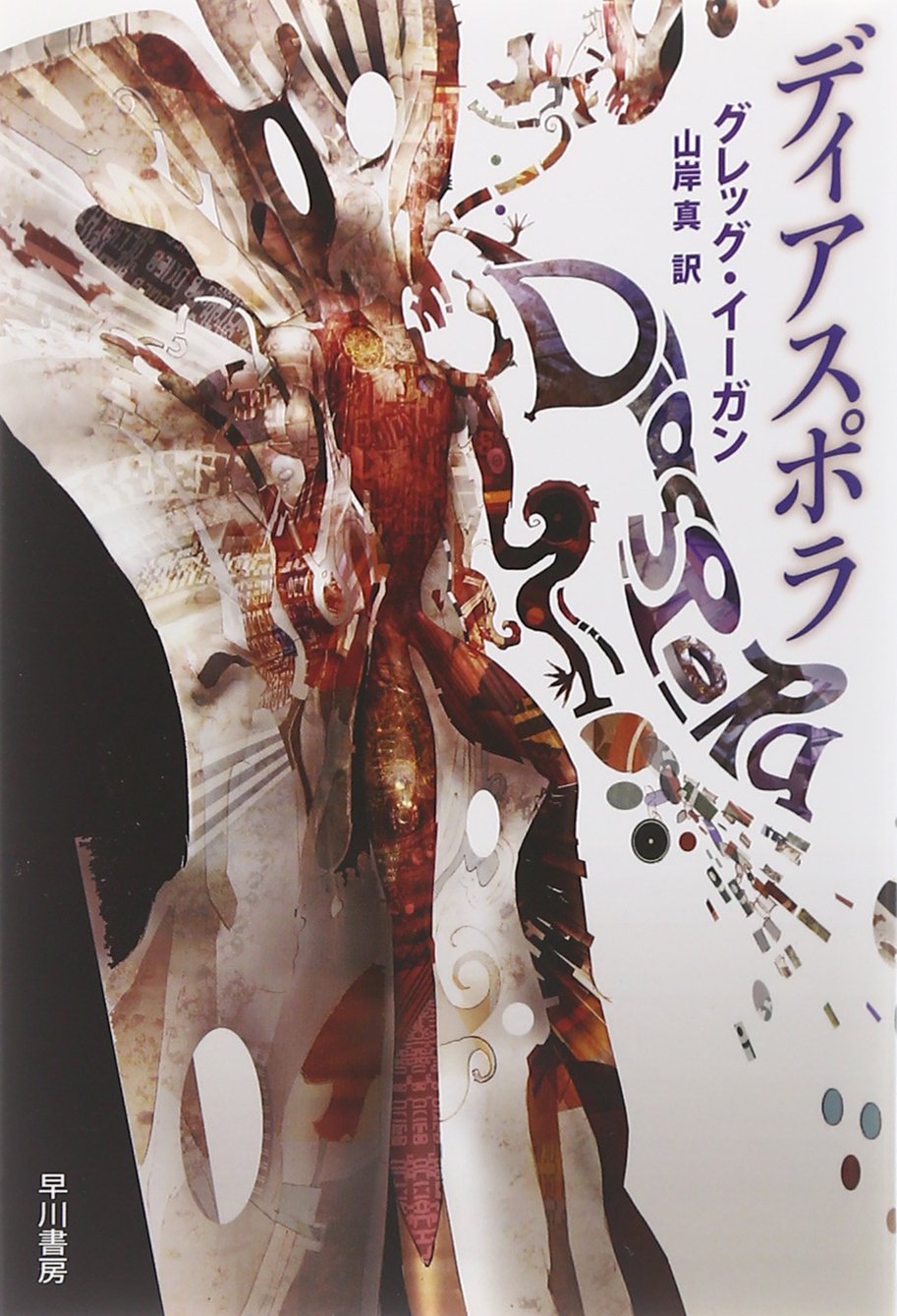
『ディアスポラ』グレッグ・イーガン =著、山岸真 =訳、早川書房
仮想空間に移住した人類が、地球を捨ててストレージごと宇宙を旅するハードSF。やがて人類は三次元空間からも離脱し、より高い次元への孤独なジャンプを繰り返していく──。構想の力強さもさることながら、その旅の最果ての描写が大変美しい。こんなに美しい終わり方をする文章がほかにあったかしら、と何度読んでも思います。専門用語が多くてとっつきづらそうに見えますが、細かい説明はどんどん飛ばして読んでも大丈夫なのでご安心を。
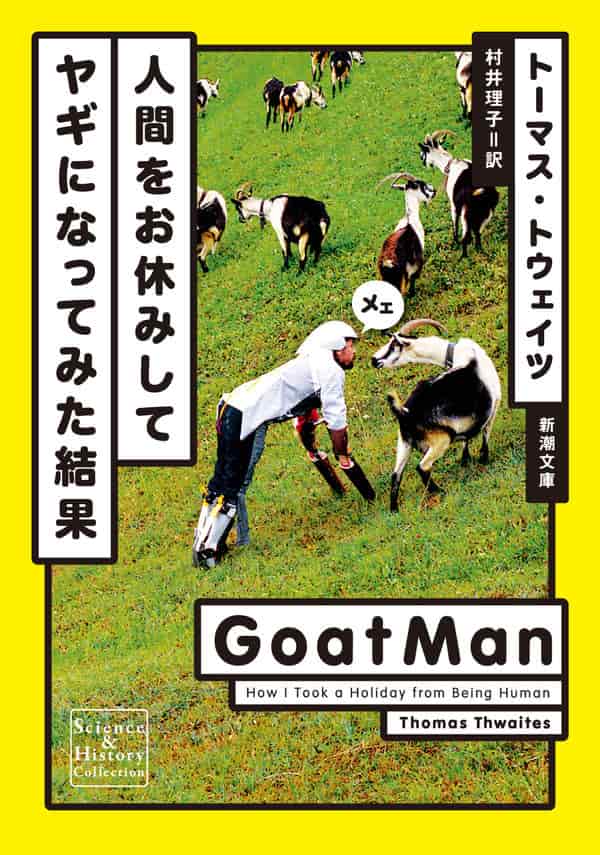
『人間をお休みしてヤギになってみた結果』トーマス・トウェイツ =著、村井理子 =訳、新潮社
文字通り、ヤギになろうとしたヒトのアーティストの話。さて、しかし、ヒトがヤギになるためにはどうすればよいのでしょうか? シャーマニズムに学ぶ意識の変容、解剖学的考察に基づく四肢装具の作成、第一胃と消化酵素の実装による草食の実現……あらゆる手段を駆使した結果、著者はめでたくスイスの山麓でヤギの仲間入りを果たします。現実空間で身体のかたちを変えてみるという実践の、貴重な記録のひとつ。
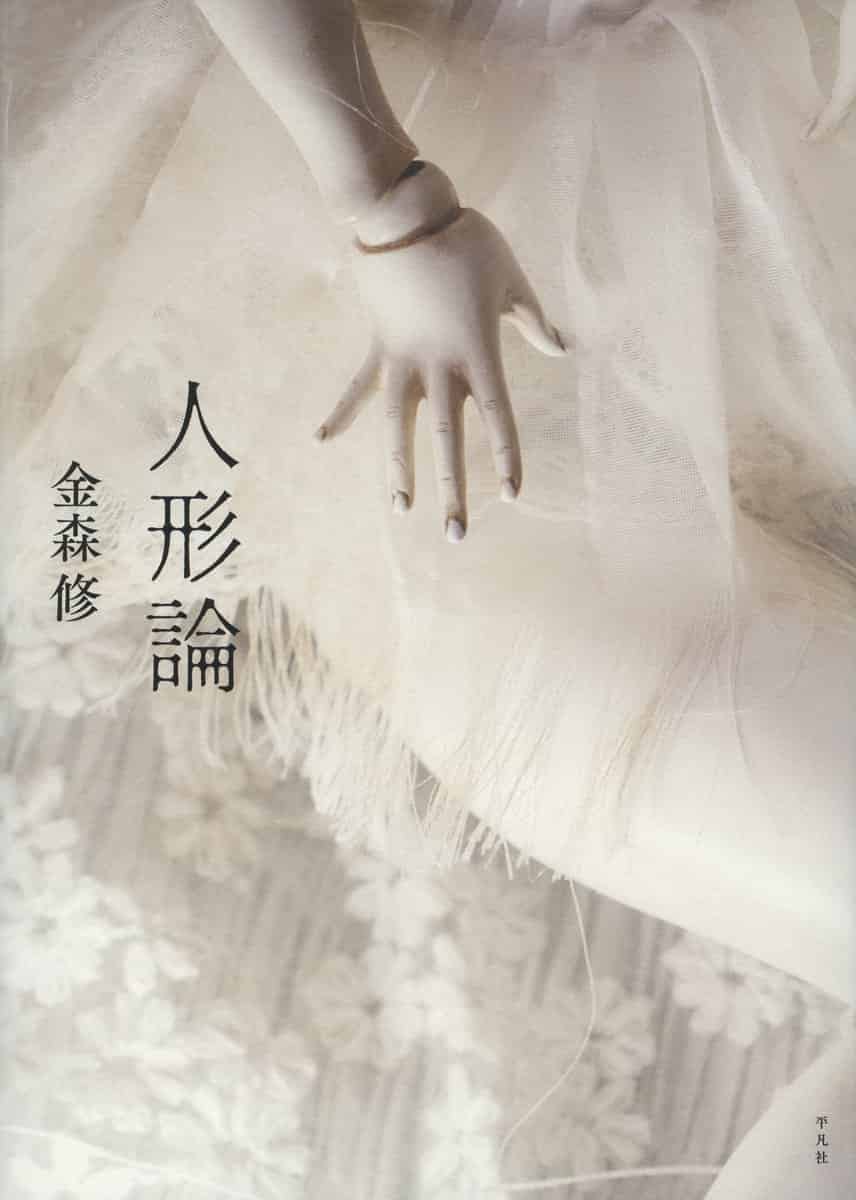
完成した人形は、人間の手を離れモノとして自存する──科学思想史家、金森修の驚くべき遺著。人形の歴史を冷静に概観する本かと思いきやそうではなくて、むしろ金森自身の独特な人形観を色濃く反映して偏っているのが読みどころ。命を吹き込まれた人形が動き出すさまを上演しているかのような、奇妙な魅力のある本です。現代の人形遊びに興味のある方は、本書が行う開眼供養の儀式から得るものがあるはず。
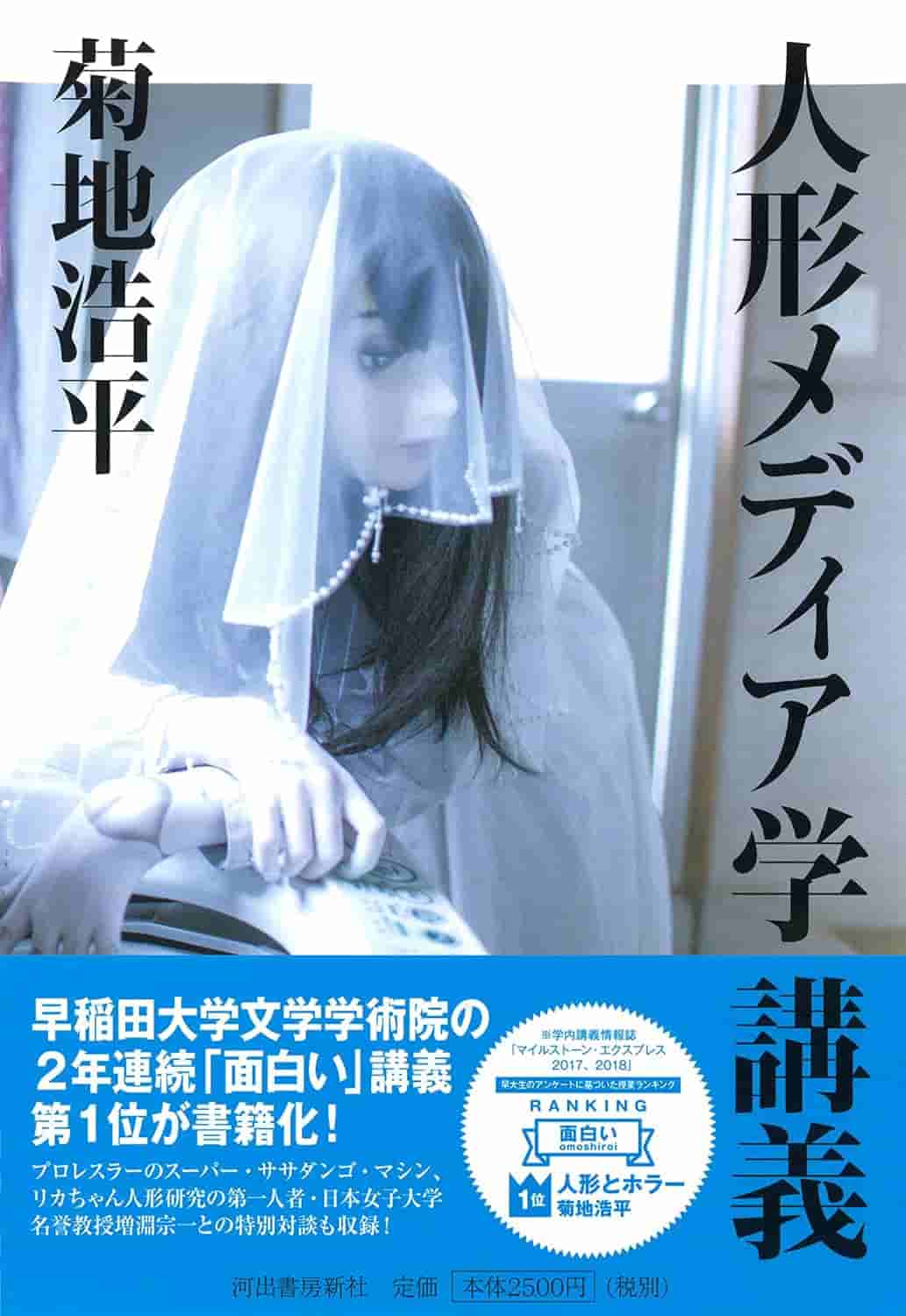
人形研究の気鋭による早稲田大学での講義録で、人形文化について何かを考えたいと思ったときには必読の一冊。人形やぬいぐるみは我々の友達であり、所有物でもあり、時にアバターでもある不思議な存在で、あらゆる切り口から論じることができる特殊な対象ではないか、というのが本書の拓いた視座だと思います。人形といいつつ、その対象の裾野が覆面レスラーやアイドルなど生身の人間にまで広がっているのも面白い。
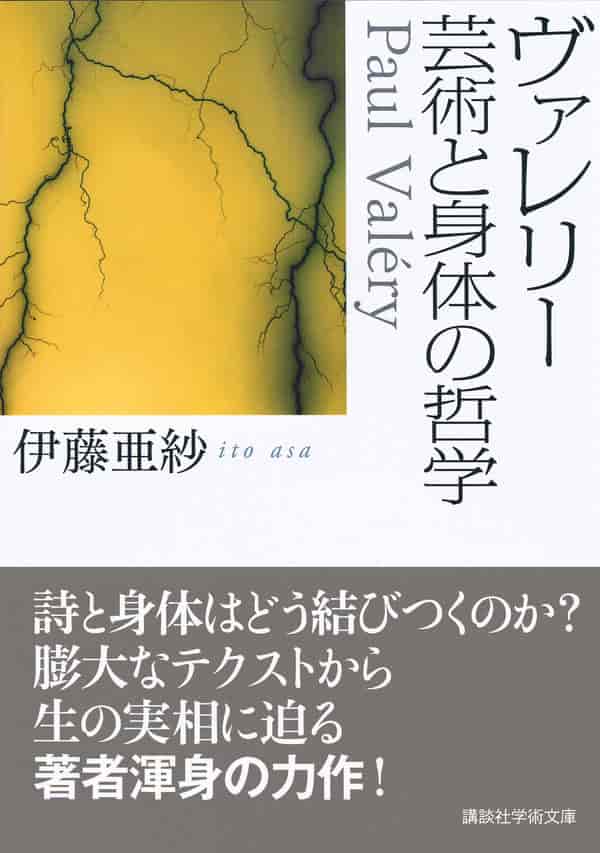
芸術は、いかにして我々の身体に介入しているか? 詩人ヴァレリーによれば、作品とは装置であり、それらは読者が自分の身体を組み立てなおし真に所有することを促しているのだといいます。詩に限った話ではありません。見立て次第ではあらゆる芸術や、日常生活の経験もまた装置なのです。「マッチを擦って火がつかない」という出来事さえひとつの詩なのだとしたら、世界は芸術に満ち満ちていることになります。
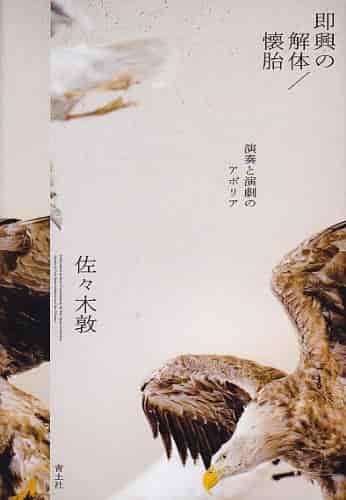
『即興の解体/懐胎 演奏と演劇のアポリア』佐々木敦 =著、青土社
「驚くべきことは、いかにして起こるのか?」舞台のうえで予想もつかないようなことが起こる、などという事態がなぜ可能なのでしょうか。音楽にせよ演劇にせよ、演者は自分の持っているカードを切り続けるしかなくて、それゆえ芸術はつねに、反復と予定調和に陥る可能性をはらんでいます。しかし、それでも現に、驚くべきことは起こるのです。演じることの不思議について徹底的に批評する本書には、何度読んでも新しい発見があります。
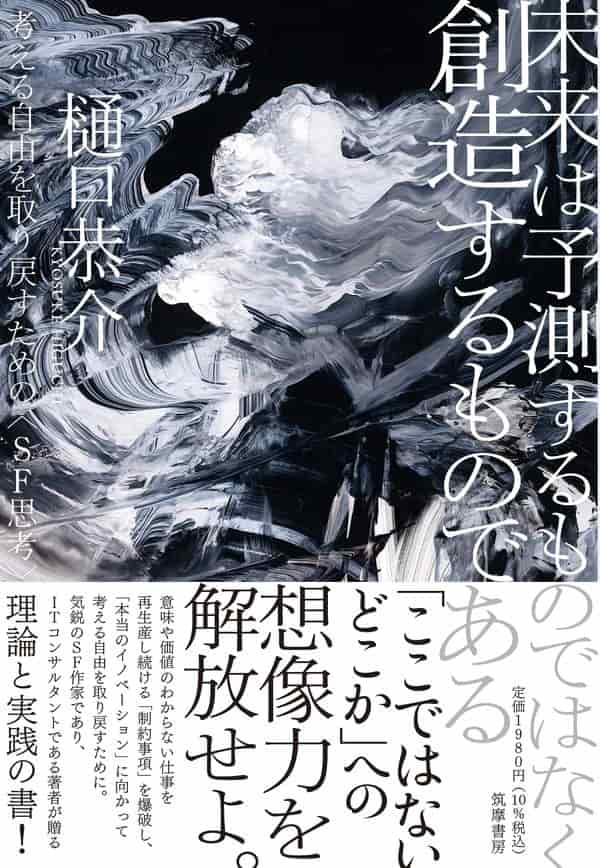
『未来は予測するものではなく創造するものである 考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』樋口恭介 =著、筑摩書房
未来は物語の力によって創造することができる。これが「SFプロトタイピング」と呼ばれる手法の中心的な主張で、本書はその具体的・実践的な入門書になります。著者は外資系コンサル勤務のSF作家という変わった人で、SFの想像力を足掛かりに未来の世界を創っていこうという本書の主張には、なにか地に足のついた迫力があります。実用書として長く読まれるべき本であり、あらゆる分野のエリートが触れておくべき本。
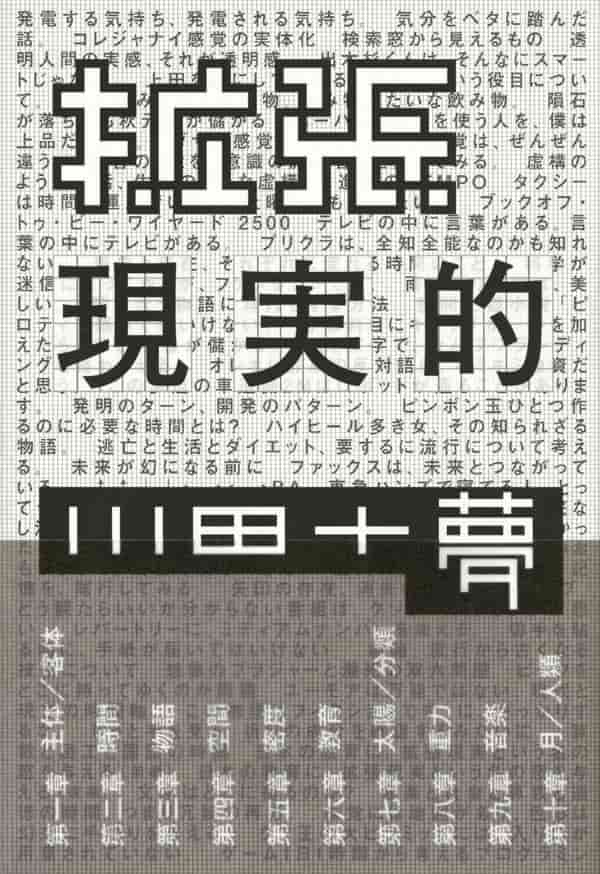
拡張現実開発ユニット「AR三兄弟」の長男が、SF的な速度でぶっ飛ばす天声人語。とにもかくにも、文体が思考をドライブする快感がたまらない一冊です。現実のなかに未来の入り口を見つけ、生活のなかで五感をシャッフルするような独特の語りを通じて、我々は「現実的ではないが、拡張現実的ではある」という事態がたしかに存在することを理解します。頭を柔らかくして読みましょう。
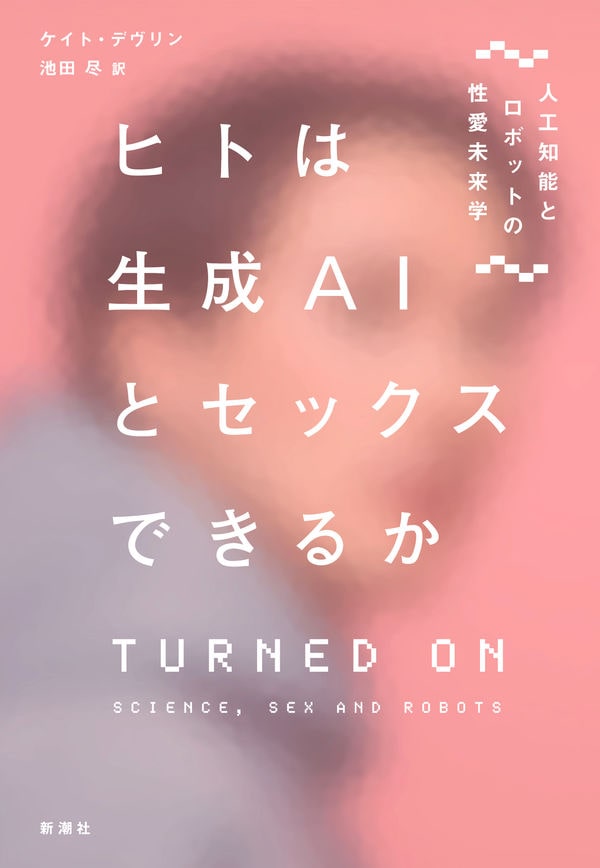
『ヒトは生成AIとセックスできるか 人工知能とロボットの性愛未来学』ケイト・デヴリン =著、池田尽 =訳、新潮社
モノとヒトとの性的な交流という切り口で、古代のギリシャ神話から現代のロボットとラブドールまで一気に駆け抜ける本。カマシ気味の邦題が秀逸で、この文言だけできわめて具体的・直感的な思考が触発されます。著者は女性、かつラディカル寄りのフェミニストで、フェミニズム的な関心が問いを駆動しているのも重要なポイント(たとえば、どうして音声アシスタントの性別は女性に偏っているのでしょうか?)。
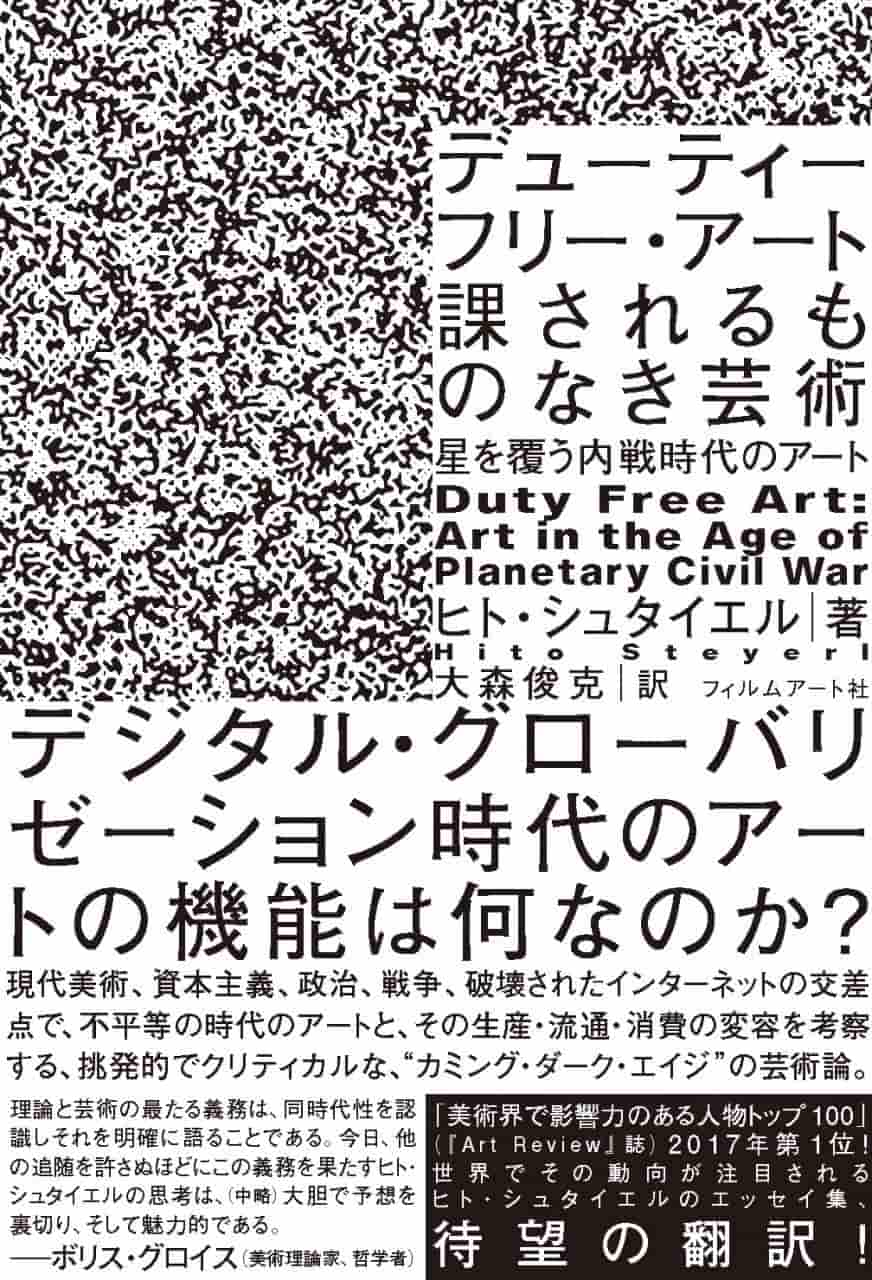
『デューティーフリー・アート 星を覆う内戦時代のアート』ヒト・シュタイエル =著、大森俊克 =訳、フィルムアート社
アーティスト・批評家のシュタイエルが、アートシーンの現在と、デジタル時代に更新された「ある」ことや「いる」ことについて論じた本です。芸術作品が複製可能なのとは対照的に、人間が「いる」という価値は複製できない。そこで我々は、「いる」ことを一時的に代替するために様々な身代わりを使います。リッピングされた身体、モノ化した現実、チャットボット……シュタイエルが「プロキシ」と呼ぶこうしたモノたちは、もはや確実に社会の構成員なのです。
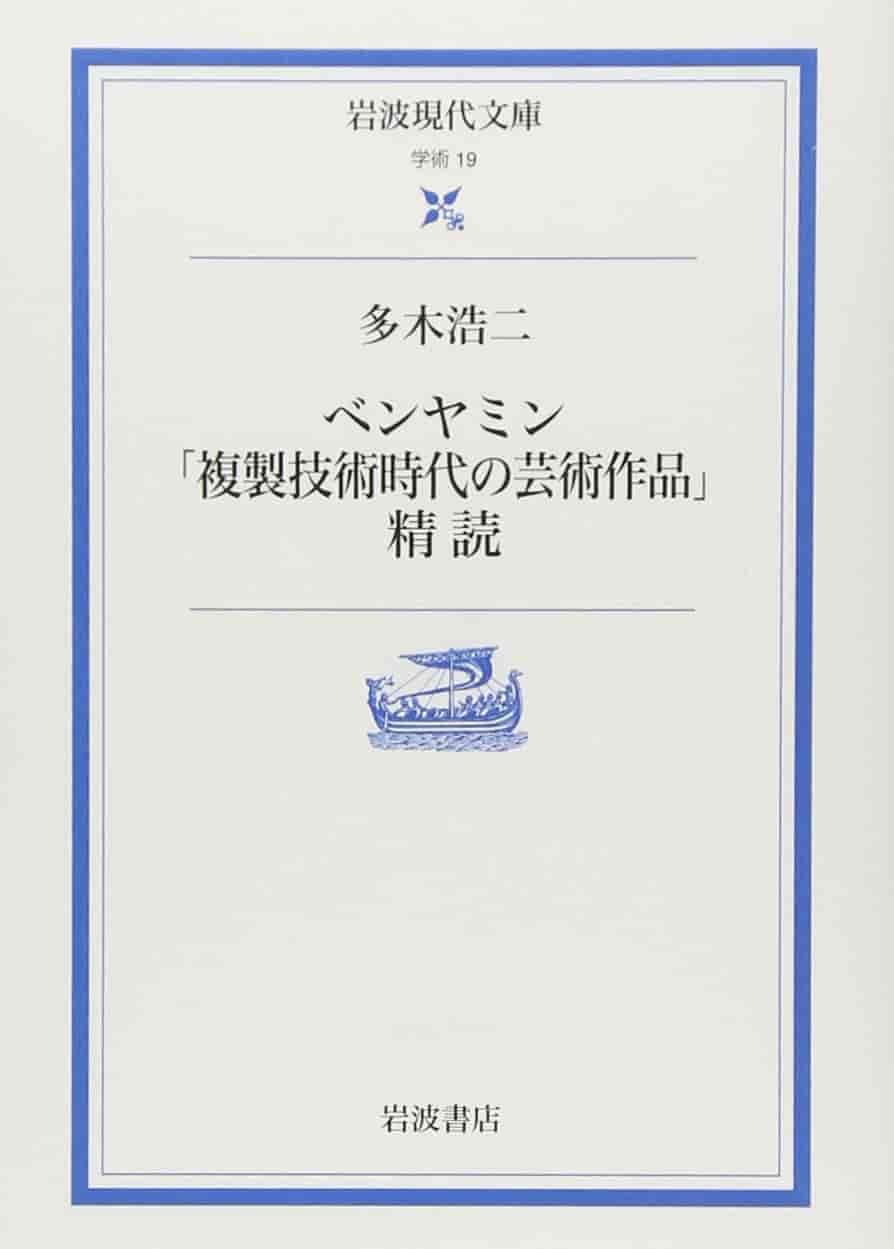
『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』多木浩二 =著、岩波書店
ベンヤミンの立てた問いは、複製技術が芸術に何をもたらしたか、というものでした。モノの複製が可能な社会で、芸術はどのような立場に置かれるのか。そもそも芸術は何を根拠に成り立つ(成り立っていた)のか。言うまでもなく、複製だらけの社会を生きる現代人にも刺さる話です。「複製技術時代の芸術」を収録した本は複数ありますが、多木浩二による長い解説・注釈を本体としたこちらが読みやすい。
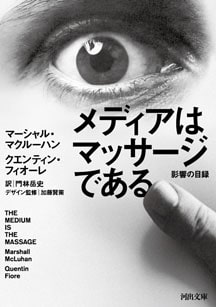
『メディアはマッサージである 影響の目録』マーシャル・マクルーハンほか =著、門林岳史 =訳、河出書房新社
拙著『踊るのは新しい体』で描いたのは、人型のモノ(我々の肉体も含め)がある種のメディアとなった今日の状況でした。基本に立ち返って、新しいメディアがいかに我々の知覚のデフォルトを変えてきたかについてはマクルーハンを。印刷、写真、輸送機関、ラジオ、テレビ……印象的なコラージュを多用した本書には、頭をもみほぐしてくれるような気持ちよさがあります。より詳しく学びたい人は『マクルーハン理論』(平凡社ライブラリー)あたりへ進むとよいでしょう。
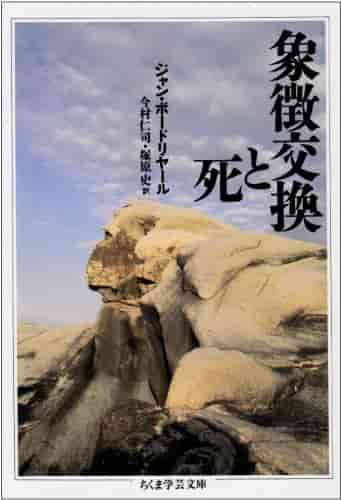
『象徴交換と死』ジャン・ボードリヤール =著、今村仁司、塚原史 =訳、筑摩書房
現代社会ではつねに、現実的なものと想像的なものとが混ざり合い、複製とオリジナルとが混ざり合っています。あらゆる現実が容易に美化され、メディアを通じてシミュレーションであるかのように経験されてしまう消費社会のありようを論じた本書は、主張の是非はさておき今日もなお面白い。個人的には自動人形やメイクアップ、ストリップを論ずるくだりなど、意外にも身体論的な枝葉が面白い本/論者でもあります。
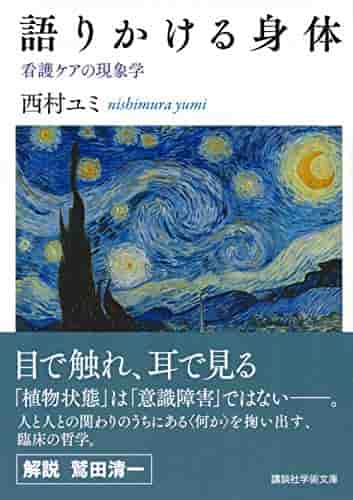
「意思疎通できない患者さん」と通じ合うこと──にわかには理解しがたい話ですが、できる人にはそれができるのです。生身の身体が持っている情報量の豊かさとは、たとえばこういうことなのでしょう。もっとも、その豊かさを受け止めるためには相応の技術が必要です。我々は、機械とAIの時代にもそれを保持し続けられるでしょうか……。看護という技術の深淵をめぐる、衝撃のエスノグラフィー。

『技術への問い』マルティン・ハイデッガー =著、関口浩 =訳、平凡社
現代技術を手にした人間が自然を資源として用立てるように、現代技術もまた人間を挑発し、用立てているのではないか。私の理解が正しければハイデガーは本書でそう言っているのですが、今日、機械とAIの時代を生きる我々には、この見立てがなんの違和感もなく理解できてしまいます。いま私たちが何に挑発されているのか、冷静に振り返るための一冊。
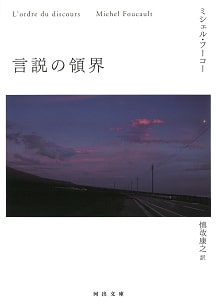
『言説の領界』ミシェル・フーコー =著、慎改康之 =訳、河出書房新社
真理はなぜ真理とみなされるのか? フーコーによれば、それはすでにある真理のシステムの働きに起因しています。誰が、何を、どのように語ることができるかは、このシステムによって規定されているというわけです。主に扱われているのは科学的言説ですが、「アートはなぜアートなのか」とか「ダンスはなぜダンスなのか」とか、色々と応用が効きます。短いし比較的読みやすいので、フーコーに触れる一冊目としてもどうぞ。
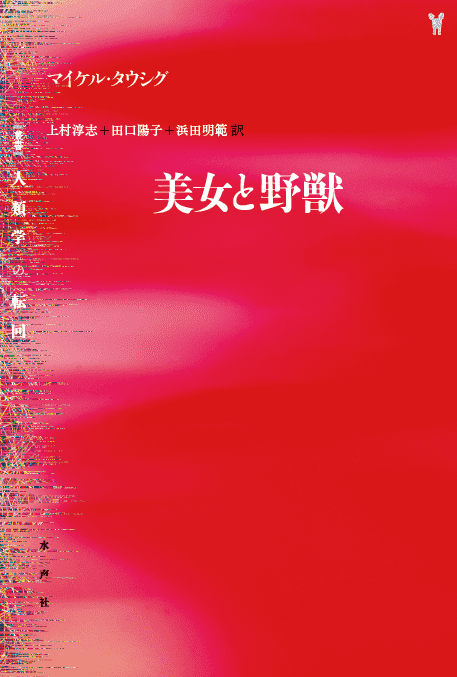
『美女と野獣』マイケル・タウシグ =著、上村敦志ほか =訳、水声社
美とは我々の生を駆動する力であり、下部構造である──「美容整形とマフィアの身体改造をめぐる人類学」という文言だけでワクワクする本書ですが、翻って、この見立ては「おじさん」たちがこぞって美少女に転生しようとする我が国の現況とも無関係ではないでしょう。アバター製作や加工アプリといった美をめぐる技術は、美容整形と同じく、「資本主義がもたらす新たな魔術」なのかもしれません。
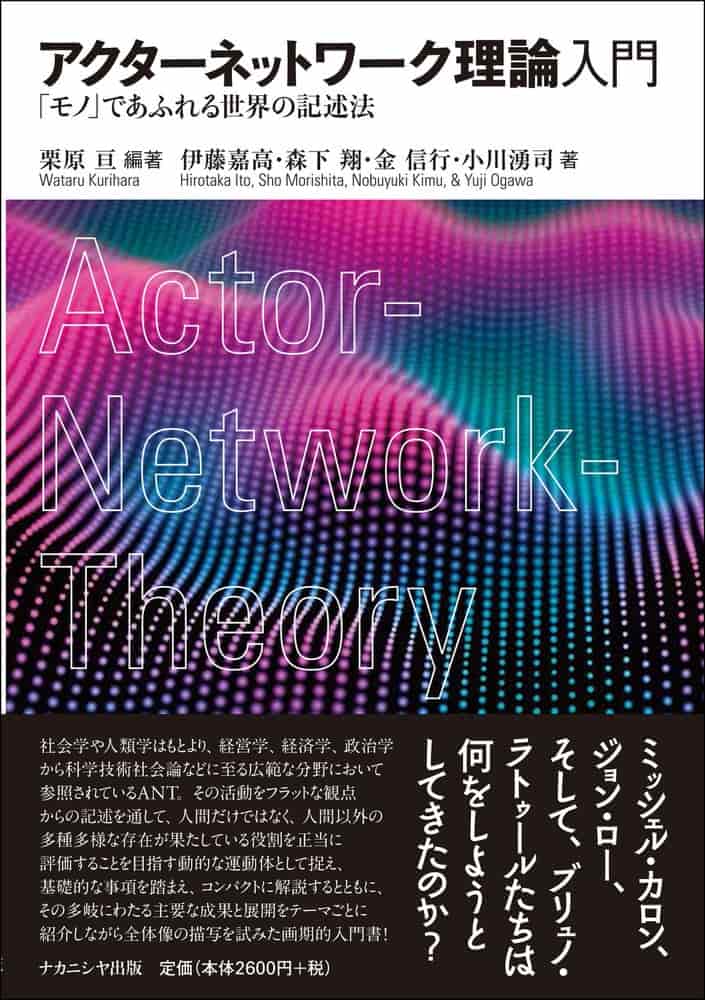
『アクターネットワーク理論入門 「モノ」であふれる世界の記述法』栗原亘ほか =著、ナカニシヤ出版
「モノ」たちはいかにして行為の生成に参与するか? 「モノ」を人間と対称なアクターとして扱う社会学の手法「アクターネットワーク理論」の数少ない入門書。入門としてはちょっと飛ばしすぎな気もしますが、x〜xi頁の「重要語句の道案内」を眺めてみて、面白そうかも、と思ったらとりあえず買ってみましょう。道案内を起点に、興味を惹かれた章からつまみ食いしていくとよいと思います。
番外編
入手困難のため、フェアから外したものを紹介します。

『未来のダンスを開発する フィジカル・アート・セオリー入門 』 木村覚=著、メディア総合研究所
【版元品切】現代ダンスの見方と、未来のダンスの作り方を論じた本。ダンスについて書かれた一般書の中で一番面白い(私見)。復刊求む。
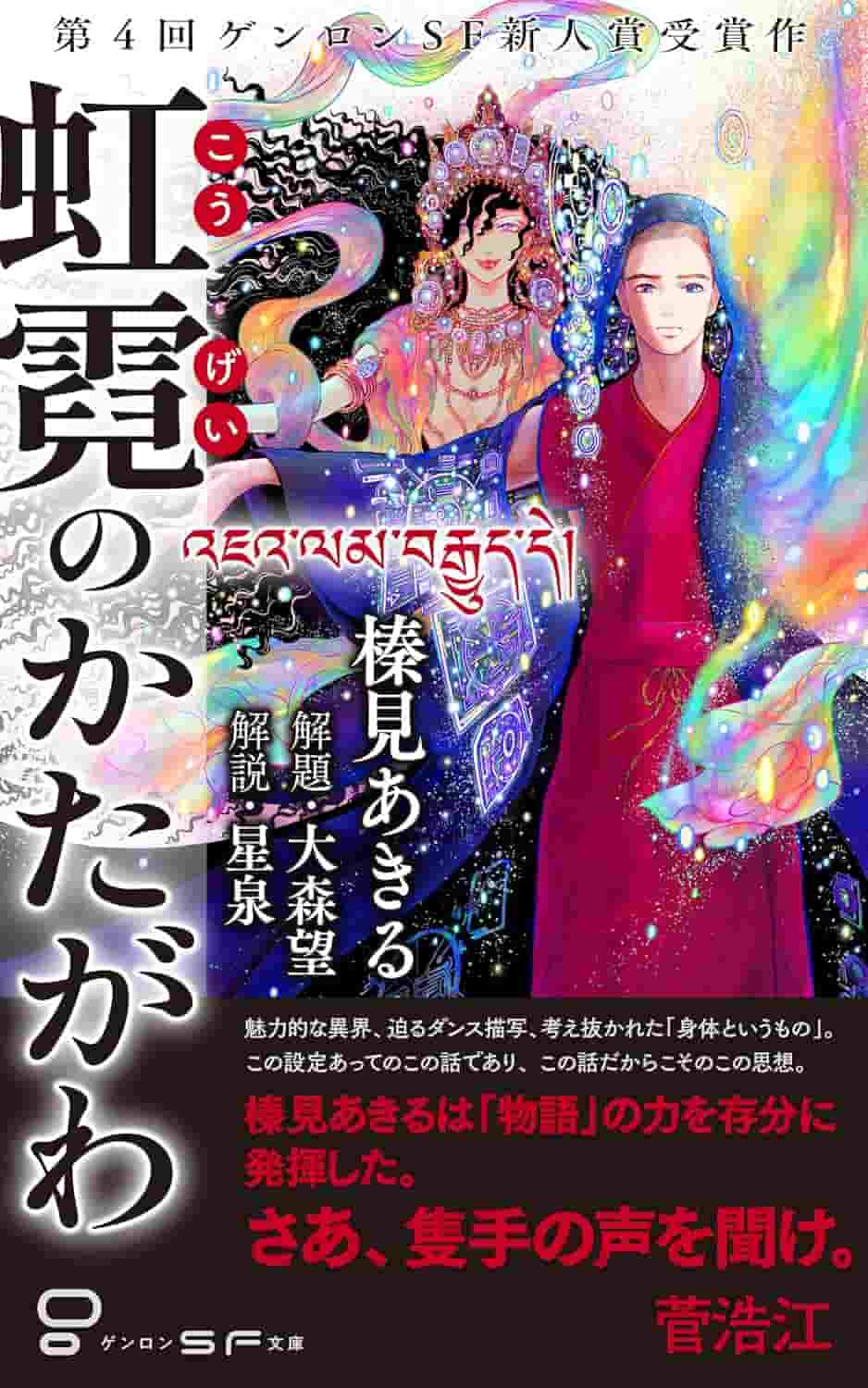
【電子書籍】技術・芸術・身体に信仰が絡んだ絶妙な世界設計のSF中編。拡張現実と融合したダンスの描写が超絶技巧の域。
【好評発売中!】
踊るのは新しい体
複製可能な者たちのための身体論
太田充胤=著
発売日:2025年3月26日