映画の制度に挑戦し、その独自のスタイルが世界を驚かせてきた映画監督・諏訪敦彦。初の単著となる『誰も必要としていないかもしれない、映画の可能性のために──制作・教育・批評』には、さまざまな場所で展開された諏訪監督の思考が凝縮されており、その全貌を知ることができる1冊となっています。
本書の刊行を記念して、選書ブックフェアを開催しました。
本記事では、諏訪監督ご自身が当フェアのためにセレクトしたリストを、各選書へのコメントとともに公開いたします。
諏訪敦彦を作った26冊
(選・文/諏訪敦彦)
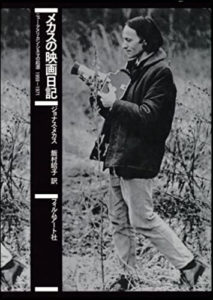
1. ジョナス・メカス『メカスの映画日記──ニュー・アメリカン・シネマの起源1959-1971』飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年
この本に出会わなかったら、私は映画を作ろうなどとは思わなかっただろう。彼がその存在をかけて紡ぎ出す言葉は、映画が生まれ変わる時代の生々しい証言であり、映画を生きることそのもののようである。

2. ロラン・バルト『明るい部屋──写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、1997年(新装版)
あらゆる現象を見事な手さばきで分析したバルトが、その晩年に、写真とは愛であるという驚くべき地点に到達するさまが私的な物語として語られる美しい書物。


3. ジル・ドゥルーズ『シネマ 1*運動イメージ』財津理・齋藤範訳、法政大学出版局、2008年
4. ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』宇野邦一・石原陽一郎・江澤健一郎・大原理志・岡村民夫訳、法政大学出版局、2006年
映画を思考することで、新たな概念を創造しようとするスリリングで壮大な試み。「シネマ2」で突如出現する「世界への信頼を取り戻すこと、それこそが現代映画の力である」という言葉が、鮮烈な呼びかけとして響く。

5. ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』望月哲男・鈴木淳一訳、筑摩書房、1995年
ドストエフスキーの小説の本質を、互いに独立した声と意識によるポリフォニー(多声楽)と、カーニバルという非中心的な形式に見出そうとする独創的な視点が展開される。50年以上前の論考ながら、むしろ現代の表現者に重要な示唆を与えると思う。
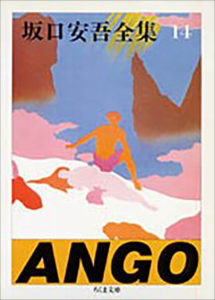
「FARCEに就て」「日本文化私観」「堕落論」など安吾のエッセイはどれも目が覚めるほど面白いが、「救いがないということ自体が救いであります」という絶対の孤独の地点に文学の(人間の)始まりを見ようとする「文学のふるさと」は秀逸な芸術論。

近年、日本でも盛んになってきた、子どもを対象とした映画制作ワークショップについて、実践例や海外での状況などを紹介し、「学ぶ/教える」という関係を超えて映画教育に何が可能かを問う一冊。

8. セルジュ・ダネー『不屈の精神』梅本洋一訳、フィルムアート社、1996年
映画を愛するもの(シネフィル)として生きることが孤独で絶望的な時代にあって、強制収容所以降の映画の倫理を問い、しかし映画が芸術=抵抗であることを信じ、夭逝するまでそれを手放さなかったダネーの最後の言葉たちは今も心に迫る。

9. エマニュエル・レヴィナス『われわれのあいだで──《他者に向けて思考すること》をめぐる試論』合田正人・谷口博史訳、法政大学出版局、2015年(新装版)
私たちは他者と溶け合うことはない。それは嘆きや悲しみを生むのかもしれないが、しかしそれは絶望ではなくそれこそが愛の卓越さなのだ、というギリギリの希望を創出する他者論集。

10. 佐藤真『日常と不在を見つめて──ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』里山社、2016年
簡単にカメラに写ることはないものを映画にしようとした佐藤真の仕事を検証し、その内的な格闘を描き出そうとする。構想中だった「ドキュメンタリーの哲学」に予告された「ブリコラージュの道具としてのカメラ」という概念が、どのような未知の領域を切り拓いたのだろうか、その可能性に想いを馳せる。

11. ペドロ・コスタ『歩く、見る、待つ ペドロ・コスタ映画論講義』土田環編訳、ソリレス書店、2018年
日本の学生の質問に真摯に答えるペドロ・コスタの言葉は、あくまで現実的な他者との関係の中で思考された職人の言葉であろうとするが、それは同時に既存の映画史を再構築する強靭な映画哲学でもある。

あの原爆の惨禍の瞬間、目の前に開けた光景を「たしか、こういう光景は映画などで見たことがある」と記す原民喜の言葉の静かな衝撃。それは、現実との絆を断ち切られた人間の精密なドキュメントでもある。
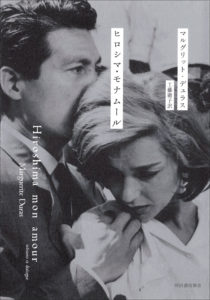
13. マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』工藤庸子訳、河出書房新社、2014年
「きみはヒロシマで何も見なかった」「わたしはすべてを見た」というダイアローグは、語り得ぬことを語る古典的な響きを持つかのようであるが、フクシマ以降を生きる私たちに、新たな愛の物語の可能性を問いかけるのかもしれない。

14. 山田宏一『山田宏一映画インタビュー集 映画はこうしてつくられる』草思社、2019年
映画を作るとは、果てしない人と人とのやりとりである。この情熱的なインタビューを読んでいると、知らないうちに「映画を作る」という熱に囚えられてしまう。貴重な証言集というだけでなく、この本では、まさに映画が作られているのである。
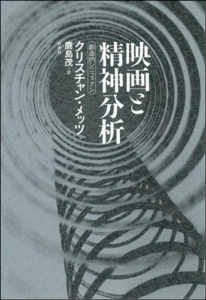
15. クリスチャン・メッツ『映画と精神分析──想像的シニフィアン』鹿島茂訳、2008年(新装復刊)
記号学によって映画を捉えるという壮大な思考実験の挫折ののちに、精神分析によって再び映画に接近してゆくメッツのスリリングな思考のドキュメントでもある。映画の観客の内で一体何が起きているのか? そして、メッツの思考には常に続きが残されている。


世界の中で唯一の存在である「この私」と「他者=世界」をめぐるこの孤独な哲学的探求は、なぜか創造し、表現する「この私」に果てし無いインスピレーションを与え続ける。
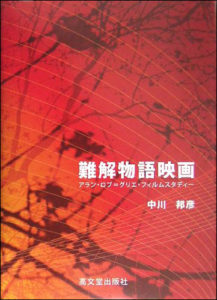
18. 中川邦彦『難解物語映画──アラン・ロブ゠グリエ・フィルムスタディー』高文堂出版社、2005年
アラン・ロブ゠グリエの映画の詳細な分析を通して、人がいかに映画の解釈を間違うのかを明らかにしてゆく驚くべき書物。そして、物語が私たちを主観性に閉じ込めてしまうことを暴いて、「他者に目を開く必要」に迫る。

19. ライナー・マリア・リルケ『オーギュスト・ロダン──論説、講演、書簡』塚越敏訳、未知谷、2004年
初めてロダンのアトリエを訪れた時、初めて彫刻というものに「精神」の形を見たような気がした。それが『不完全なふたり』のインスピレーションであったが。リルケは、息を飲む美しい言葉によってその精神を彫刻するかのようである。

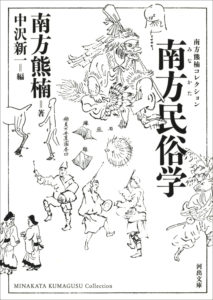

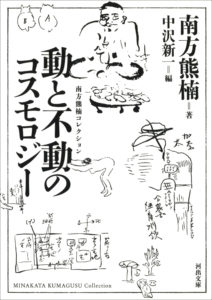
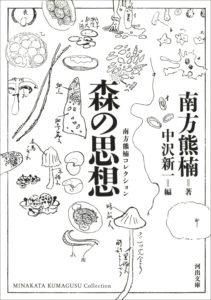
20. 南方熊楠『南方マンダラ』中沢新一編、河出書房新社、2015年(新装版)
21. 南方熊楠『南方民俗学』中沢新一編、河出書房新社、2015年(新装版)
22. 南方熊楠『浄のセクソロジー』中沢新一編、河出書房新社、2015年(新装版)
23. 南方熊楠『動と不動のコスモロジー』中沢新一編、河出書房新社、2015年(新装版)
24. 南方熊楠『森の思想』中沢新一編、河出書房新社、2015年(新装版)
粘菌から森、宇宙、民俗、宗教へと整然と分類された縦割りの学問を縦横無尽に横断し、マンダラとして全くオリジナルな学問を出現させる南方学の現代性は未だ汲み尽くされていない。
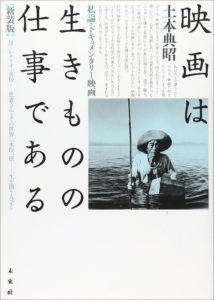
25. 土本典昭『映画は生きものの仕事である──私論・ドキュメンタリー映画』未來社、2004年(新装版)
水俣病を追い続けた土本典昭監督のドキュメンタリー映画論。「生きている人形」と言われた患者にカメラを向ける時、カメラを持った男は映画の絶対零度のような葛藤を通り抜けてゆく。「映画をつくることは、人と出遭う事業」なのである。
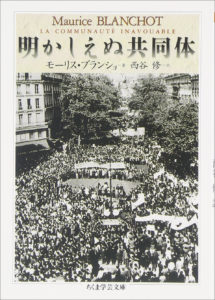
26. モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』西谷修訳、筑摩書房、1997年
俳優ジャン゠ピエール・レオーとよくブランショのことを話した。68年5月という革命の時を経て、「共同体」と呼ばれたものがいかに裸形の関係である「愛」に至るのかが映画的とも言える魅惑的な文体で語られている。