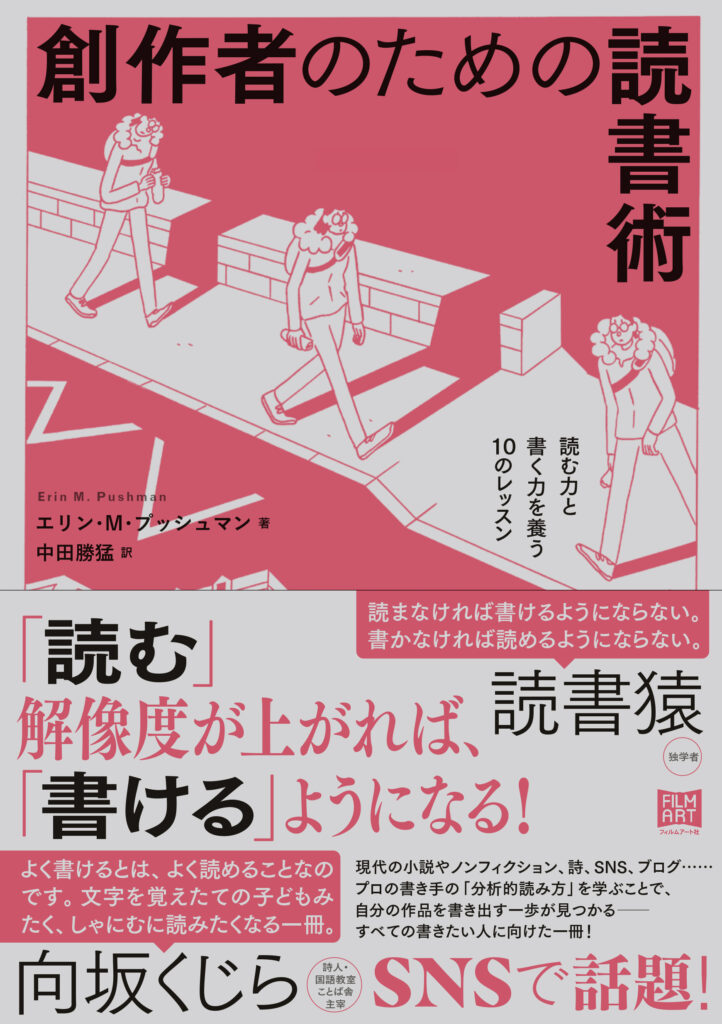第1章 ジャンルについて
ジャンルという概念
定義の話から始めよう。書き手が何かを書こうとするとき、それは「特定のジャンルや型のなかで書く」ことを意味する。ジャンルに着目することで、書き手が特別な物語や特殊な考えを語ったり伝えようとするときに、どうして特定のジャンルを選んだのかが理解しやすくなる。「特」がつく言葉を使いすぎてるように見えるが、作家とは独特な人間なのでしょうがない。とにかく、作家は読んでいるとき――書いているときと同じように――ジャンルに着目していることを覚えておこう。
では、次の一文を読んでほしい。
私は六歳のとき、妹を撃ち殺してしまった。銃の使い方なんて知らなかったのに。
つかみの良い書き出しだと思わないだろうか。ところで、これは何の書き出しだろう? 物語? 回想録? それとも詩? どうしてこれが大事なのかというと、実話なのかフィクションなのかは、私たちにとってさまざまな意味で重要なことだからだ。
私たちは読み手として、フィクションとノンフィクションでは違う読み方をするし、ノンフィクションと詩でも違う読み方をする。つまり、ジャンルは読み方に影響を与える。そして、ジャンルがどのように影響を与えているのか考えることは、作家のように読むために必要な第一歩だ。
創作の場合、散文〔物語を語るときに使われる文体のこと〕で書かれたジャンルはフィクションとクリエイティブ・ノンフィクションに分けられる。また、クリエイティブ・ノンフィクションは文芸ノンフィクションと呼ばれることもある。ジャンルと読み方の関係を考える手始めとして、まずは散文で書かれたジャンルについて考えてみよう。
では、冒頭で取り上げた文章にもう一度戻って、今度は小説、フィクションの書き出しだと思って読んでみよう。
私は六歳のとき、妹を撃ち殺してしまった。銃の使い方なんて知らなかったのに。
フィクションの書き出しとして読んだとき、どんなことを考えていただろうか? 物語が好きな読者なら、一体何が起こったのか不思議に思い、続きを読みたい衝動に駆られるはずだ。書き手としてこの文を読んだとき、次のようなことを考えていたかもしれない。
・語り手の紹介(妹を殺した私)
・対立構造の提示(銃、妹殺し、銃の使い方を知らなかったこと)
・言葉の使い方(わかりやすく単純な言葉で、興味深い構造をもつ文であること――結論を先に出し、助詞で文を終わらせている)
フィクションを読んでいるとき、読者の関心はキャラクターたちと、彼/彼女たちが織りなす出来事に集中する。あなたのお気に入りの小説を思い浮かべてみてほしい。キャラクターたちとその出来事に興味がなかったと言えるだろうか――そんなことはできないだろう。現実の人物でも出来事でもないとわかっているにもかかわらずだ。
では、また先ほどの文章に戻る。今度は回想録、つまりクリエイティブ・ノンフィクションの一種の書き出しとして読んでみよう。
私は六歳のとき、妹を撃ち殺してしまった。銃の使い方なんて知らなかったのに。
クリエイティブ・ノンフィクションとしてこの文章を読んだ場合、文字通り話が変わってくる。何が起こったのか不思議に思い、続きを読みたい衝動に駆られるのは同じだが、それが現実に起こったことだと知るのだ。どこかに実在した六歳の子どもが、自分の妹を実際に殺してしまったのである。そして書き手としてこの回想録の書き出しを読んだとき、以下のようなことを考えたかもしれない。
・キャラクターとして語り手を紹介していること。たとえ、それがこの文章を書いている実在の人物で、子どもの頃に自分の妹を殺したことがあったとしても
・対立構造の提示をしつつも、正直に語っていること(妹は実際に死亡し、語り手は本当に六歳だった)
・言葉の使い方(わかりやすく単純な言葉で、興味深い構造をもつ文であること――結論を先に出し、助詞で文を終わらせている)
クリエイティブ・ノンフィクションを読んでいるとき、読者の関心は何が起こったのかを知ることであり、それが世界にとって、あるいは周囲の人たちにどんな意味があるのかということだ。
ではもう一度読んでみよう。次は詩の書き出しとして。
私は六歳のとき、妹を撃ち殺してしまった。銃の使い方なんて知らなかったのに。
この文章はあまり詩のように見えないと思うが、どうだろうか。その通り、これは詩とは言いづらい。では、その理由を考えてみよう。右の文では、完結する文が一直線に、散文のように書かれているのがわかるだろうか。一般的なルールとして、完結する文が一直線に書かれているのが散文である。もちろん、創作において例外はいつでもあり得る。その一つが、散文の詩だ。詳しくは第2章で扱うが、この文を詩の一つのフレーズとして読んだ場合、どうして文法的に正しく完結した文でなければならないのか、どうして一行はこんなに長いのかと不思議に感じてしまうだろう。
右の文を詩の文として考えるなら、次のようなものを想像するかもしれない。
私は
六歳のとき
妹を
撃ち殺して
しまった
銃の
使い方なんて
知らなかった
のに。
この九行を詩として読もうとすると、散文で読んだときと比べて、それぞれの言葉にまったく違う読み方をしているはずだ。私たちは詩に対して、言葉の意味と同じくらい表現やリズムに注意を向ける。詩として読んだとき、以下のようなことを考えていたのではないだろうか。
・感情、経験、語りを伝えるために適切な言葉を使っているか
・リズムと響きを感じられるか
・詩行や詩節(連)の形になっているか(改行するまでに何文字あるのか、全体でどんな形になっているか)
また、詩に込められているものも散文のときとは異なっている。読者は、詩がどれだけ琴線に触れるか、その言葉がどれだけ感情に訴えているかに注目する。
私たちは普段、次は何が起こるのだろうと思いながら詩を読むのではなく(語りの詩は除く) 、感覚的なものや深い感動を得ようとして詩を読む。そして言葉の響きと詩のリズムに身を委ね、詩のレンズを通して世界を見ようとする。言葉、リズム、イメージ、そして感性を、詩から得るのだ。
では、真実という概念について戻ってみよう。詩とは真実を伝えなければいけないのだろうか? 詩における真実をめぐる議論は複雑であり単純でもある。つまり、詩は真実を伝えることが多いが必ずしもそうである必要はない、ということ。多くの書き手が、詩人が誠実であればあるほどその詩も豊かになると思っている。しかし、詩人のなかには物語やキャラクター、出来事をつくり出すものもいる。『老水夫行』 〔イギリスの詩人サミュエル・テイラー・コールリッジの代表作〕はその古典的な例だ。
現代詩人の多くが、自身の経験に根ざした誇張なしの事実を書くことを選んでいる一方、経験したことがないことについて書く詩人もいる。詩人には、人生や人間の本質についての真実を映すキャラクターや出来事を発明する自由がある。これが詩的真実と呼ばれるものだ。妹と銃の例をもう一度見てみよう。私は六歳のとき、自分の妹はもちろん誰のことも撃ったことはないのだが、このような悲劇は現実に起きていた。詩行は、この種の悲劇を反映し熟考させる言葉を、読者に与えるのだ。
創作のジャンルは常に辞書の定義以上の存在だ。人間と同じように、ジャンルもまた、それを定義するために使う言葉以上のものなのだ。私たちは作家であり、私たちの仕事は言葉を扱うこと。そこで、共通の理解を得るために、ジャンルを定義するうえで基本となる用語を整理しよう。
※続きは書籍でお楽しみください
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。