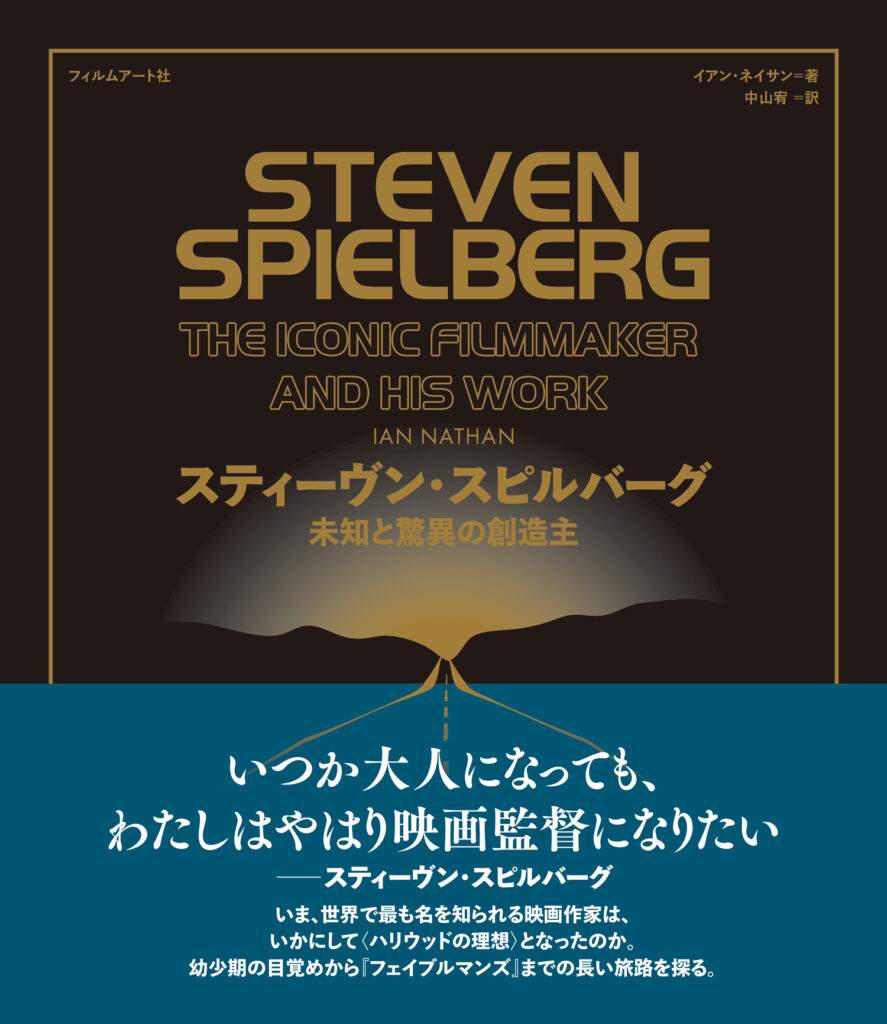オープニング
「僕は映画をつくるつもりだ。監督も製作もやる」
──スティーヴン・スピルバーグ、第8学年〔日本の中学2年生に相当〕
始まりは一本の電話だった。わたしのデスクの上の黒電話が突然、けたたましく鳴り響いた──とそれはまあ、もののたとえだが、意味はわかってもらえるだろう。映画なら、そんなふうに描かれるシーンだ。
「スピルバーグはどうです?」出版社の担当編集者が、この世でいちばん簡単な問いかけであるかのように提案を投げてきた。わたしたちは、今後刊行する本の企画をめぐり、どんなテーマや有名監督を取り上げようかと検討している最中だった。
正直に言うと、まさか現代を象徴する大物監督の名前が挙がるとは予想していなかった。わたしの頭の中でモンタージュの上映が始まった。自分自身の子供時代が甦り、さまざまなフラッシュバックが心の中の銀幕で揺れ動いた。「スピルバーグはどうです?」。尻込みしたくなるような、それでいて胸の高鳴る提案だった。
いちど立ち止まって考えてみよう。まずはっきりさせておきたい。スティーヴン・スピルバーグは、これまで存在した中で最も有名な映画監督だ。映画というメディアを定義する芸術家であり、ハリウッドの理想そのものといえる。映画の創造的な可能性と商業的な勝算を見事に結びつけた存在。すなわち「芸術」と「商業」の融合だ。
スピルバーグは、現代の単純な計算式を超越している。現象であり、幻影だ。親近感の湧く雰囲気を漂わせつつ、光を使い、数かぎりない観客にストーリーを語りかける才能を持つ。非凡なものを平凡に、平凡なものを非凡に感じさせることができる。彼の映画の主人公たちには、ある共通点がある。インディ・ジョーンズであれ、エイブラハム・リンカーンであれ、トム・ハンクスが演じたどのキャラクターであれ、弱さを抱え、過ちを犯し、かつ、何かを追い求め続ける心を持っている。
すなわち、「人間らしさ」を備えているのだ。
これほどまでに輝かしいキャリアを解き明かすためには、スピルバーグをいったん伝説的な地位から引き下ろし、彼自身が生み出したヒーローたちと同じレベルの「人を惹きつけてやまない存在」として見つめ直す必要がある(2022年の『フェイブルマンズ』では、彼自身がヒーローになったわけだが)。神格化された──聖なる「ブランド」となった──彼のヴェールを剝がし、その奥にある芸術家としての姿、映画監督としての姿、そして素の人間としての姿を再発見しなければならない。彼の原動力は、多面的な才能だ。デイヴィッド・リーンやジョン・フォードの壮大なスケール感、アルフレッド・ヒッチコックのスリル、スタンリー・キューブリックの緻密さ、ウォルト・ディズニーの心を揺さぶる力、フランソワ・トリュフォーの自然主義が見事に融和している。
彼自身の物語には、じつに多くの要素が詰まっている。映画に自伝的な色彩を宿らせた、ノスタルジックな雰囲気の郊外育ちという背景。ジョージ・ルーカスをはじめとする若手映画監督グループ、いわゆる「ムービー・ブラッツ」との交流。作曲家のジョン・ウィリアムズ、編集技師のマイケル・カーン、俳優のリチャード・ドレイファス、ハリソン・フォード、トム・ハンクスとの共同作業。映画界の大物であり師でもあるユニバーサル・スタジオの幹部、シド・シャインバーグからの信頼と支援。一連の映画制作を通じて、神話が──まさにハリウッドの伝説が──綴られていった。『ジョーズ』では悪夢のような撮影と厄介なサメのトラブルに悩まされた。『未知との遭遇』で独創的なテーマを追求したあと、『1941』では惨敗。その後、『インディ・ジョーンズ』を生み出し、『ジュラシック・パーク』でブロックバスター映画のあらたなかたちを築き、『シンドラーのリスト』では歴史の最も暗い闇へ踏み込んだ。『プライベート・ライアン』ではジャンルに革命をもたらした。『マイノリティ・リポート』『ミュンヘン』『リンカーン』では、骨太で予測不能で挑戦的な映画をつくり上げた。
そして彼自身は、控えめなセレブであり、権力の仲介が得意なやり手であり、妥協を許さない芸術家でもある。きわめて個人的な衝動に突き動かされている。しかし往々にして、自身に対する疑念に苛まれる。彼が手がけた34本の長編映画(日本やヨーロッパでは劇場公開されたテレビ映画『激突!』を含む)を結ぶ一貫した感情の糸があるとすれば、それは「不安」だ。
スピルバーグにまつわるイメージの多くは明らかに間違っている。たとえば「観客に幸福を与える、サンタクロースのようなハッピーな監督」や「偉大なる感傷主義者」。しかし、彼の映画を実際に観れば、彼は世間が思うよりずっと暗い側面を持っていることに気づくはずだ。多くの場合、観る者の心に深く響くのはその暗さなのだ。
スピルバーグは、表向きの振る舞いが控えめで、あたかもハリウッドという舞台でたやすく成功を収めたかのように見える。しかし、みずからの人生と作品、映画という媒体や世界全体への理解が、深く絡み合っているからこそ、卓越した地位を築くことができたのだ。『フェイブルマンズ』よりもはるか前から、彼の作品中の登場人物は自伝的な要素を帯びている。彼の少年時代の面影が感じられる『E.T.』のエリオット、危機一髪に陥っても肩を軽くすくめてさらりと切り抜けるインディ・ジョーンズ、「行き場を失った少年」の境遇から這い上がって自力で人生を切り開く『太陽の帝国』のジムや『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』のフランク・アバグネイル・Jr。さらに、現実の世界で奮闘した人々──オスカー・シンドラー、エイブラハム・リンカーン、『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』でトム・ハンクスが知的に生き生きと演じた「ワシントン・ポスト」紙の編集者ベン・ブラッドリー──にも、スピルバーグ本人とだぶる部分が見てとれる。
ユダヤ教の信仰との複雑な関係は、『シンドラーのリスト』の制作で初めて真っ正面から取り上げられたが、初期のころからつねに見え隠れしていた。家族というテーマも大きい。キャリアの後期に入り、世間から広く称賛され崇拝される存在となってさえ、彼の作品はいつも、両親からの承認を求め続けていた。と同時に、映画業界人たちからの承認も……。待望のオスカーを手にするまで、どれほど長い時間がかかっただろう。彼の映画づくりは一貫して、「つながり」を見つけることに関連している。
スピルバーグは奇妙なほど自己批判的であり、自分の映画の弱点を真っ先に挙げる。批評家よりも先回りする。たとえば彼は「『ゴッドファーザー』(1972)ほどの優れた映画をつくったことはいちどもない」と語る。しかし、その言葉に反論するのは簡単だろう。それぞれ舞台やジャンルが異なるものの、『E.T.』『シンドラーのリスト』『ジョーズ』『リンカーン』といった多様な映画は、傑出した価値を持つ。ただ、圧倒的な人気の高さのせいで、偉大さが埋もれがちなのだ。これほどまでに人気のある作品が、どうしてこんなに優れているのか? 不可解さゆえに、アカデミズムは彼を正面切って批評しようとしない。
スピルバーグの映画を定義し、評価し、文脈化し、理解するのは容易ではない。シンプルなのは、うわべだけだ。視覚的な魅力、観客や批評家の称賛、作品を受け入れることで得られる純粋な喜びなどを取り払って、映画制作の核心に迫る必要がある。インスピレーションの源泉や、彼の体内で脈打つ「古きハリウッド」の伝統を探らなければならない。必然的に、代表的なシーンの数々を探究し、整理・分類していくことになる。『未知との遭遇』のクライマックスにおける「マザーシップ〔=母船〕」の着陸、『E.T.』で空へ舞い上がる自転車、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』で冒険好きの考古学者を追いかける巨大な岩、『シンドラーのリスト』でのユダヤ人居住区の一掃、『プライベート・ライアン』でのD-デイ上陸……。挙げていくと、きりがない。突き詰めて言うなら、スピルバーグの天才性は、彼の象徴的なショットに宿っている。みずから慎重に選び取った映画制作の手法の表われだからだ。
わたしの前に立ちはだかる難題は、インディ・ジョーンズのシリーズに登場する罠だらけの墓のように危険に満ちていた。スピルバーグをあらたな視点から見直さなければならない。
だからこそ、わたしは「やります」とこたえ、思い切って飛び込んだ……。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。