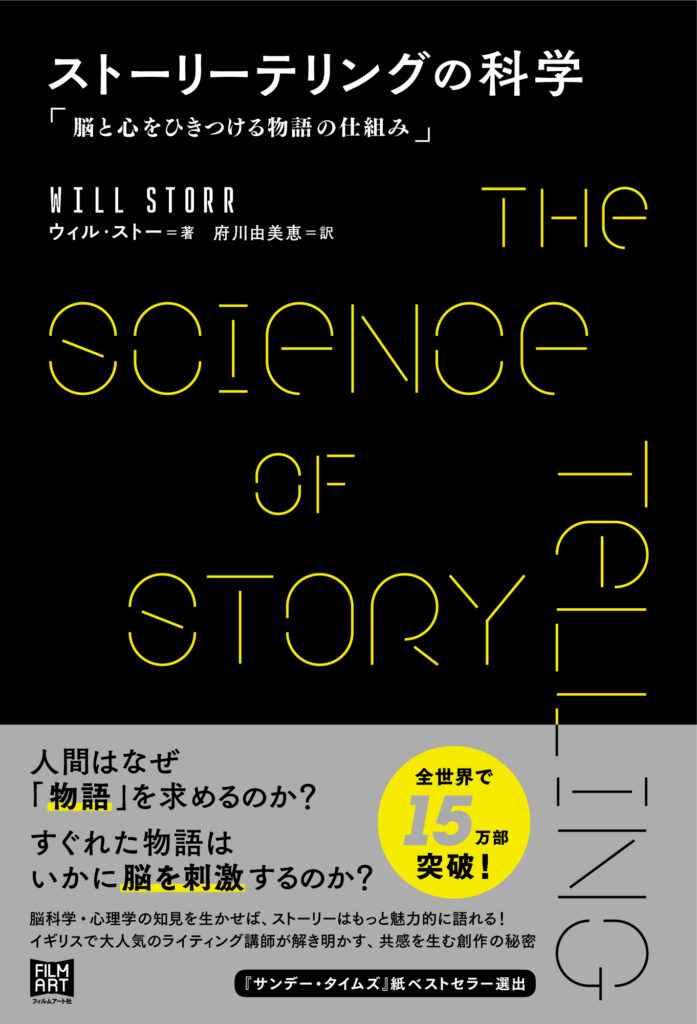はじめに
どう終わるかを、われわれは知っている。自分も、自分の愛するすべての人々も、いずれは死ぬ。その後、熱力学的死がやってくる。宇宙で起きている変化がすべてやみ、星々が死に、そして何もかもがなくなり、ただ無限の、完全な、凍てつく無だけが残る。あらゆる騒々しさや傲慢さに包まれた人間の人生も、永遠に無意味なものとなる。
しかしわれわれは、そんなふうに人生を生きてはいない。自分たちなりに、われわれの存在が本質的に無意味なことを知ってはいるが、知らないふりをして生きている。自分たちの頭上で無という事実が羽ばたいていても、何分、何時間、何日も、嬉々として逃げ回っている。真っ向からその事実を見つめ、対処するために完全に理にかなった絶望に落ちていこうとすれば、メンタルヘルスに問題ありと見なされるだろう。
この恐怖を癒やすのが物語だ。人の脳は、この恐ろしい真実からわれわれの目を逸らさせるべく、希望ある目標で人生を埋め、そのために努力するよう励ましてくれる。われわれの欲しいもの、それを手に入れる闘いの紆余曲折が、すべての人々の物語となる。物語が人々の存在に意味という幻影をもたらし、恐れから目をそむけさせる。端的に言って、物語なしに人の世界を理解するすべはない。物語は、新聞、法廷、競技場、議場、学校の遊び場、コンピューターゲーム、歌の歌詞、個人の思考や公の対話、
そして目覚めているか眠っているかに関係なく、夢の中をも埋め尽くしている。物語はどこにでもある。物語はわれわれだ。
われわれを人間たらしめるのは物語である。最近の研究によれば、石器時代の人々が生きていたころから、言語はもっぱら「社会的情報」の交換をするために進化したと考えられている※1。つまりは噂話をするためだ。人々は他人の道徳的善悪について話し、悪いおこないを罰し、善いおこないに報い、そうすることで全員が協力し合い、部族を維持してきた。英雄の物語であれ、悪党の物語であれ、喜びや怒りの感情を誘発する物語であれ、物語は人間の生き残りにとって非常に重要なものなのだ。人間は物語を楽しむようにできている。
一部の研究によれば、こうした部族の中で重要な役割を演じるようになったのは、祖父母たちだったという※2。年長者たちはさまざまな物語を語り聞かせた──祖先の時代の英雄、刺激的な冒険、精霊や魔法についての物語を※3。子どもたちはその助けを借り、物理的・精神的・道義的な世界を渡っていく。こうした物語から、複雑な人間文化が浮かび上がってきた。家畜を飼い育てはじめた部族が定住し、徐々につながって国家を形成すると、焚き火の前で祖父母が語った物語は、大勢の人間をひとつにする力を持った強大な宗教になっていった。近代国家でさえ、人々が所属する集団の物語を中心に規定されている。国の勝利や敗北、英雄や敵、独自の価値観や生き方、そうしたすべてが、自分たちが語って楽しむ物語に埋め込まれている。
われわれは、毎日の生活を物語モードで体験している。その中に生き、仲間や敵とともに暮らしていく世界を、脳がわれわれのために生みだしてくれる。混沌とした冷酷な現実をシンプルで希望のある物語に変え、その中心に、人生のプロットとなる一連の目標に沿って進むひとりのスター──すばらしい、大切な〝私〟──を置く。物語とは、脳の仕事なのだ。心理学教授のジョナサン・ハイトは、脳は「物語の加工装置」であって、「論理の加工装置ではない」と述べている※4。物語は、口から漏れる呼吸のように、人間の思考から自然に表れる。どんな人にもその手際が身についている。誰もがすでにやっていることだ。物語の話術に長けるということは、ただ自分の内面を見つめ、思考そのものを熟視し、それがどうおこなわれているかを知ろうとすることなのだ。
〈中略〉
実践的なストーリーテリングにはあまり関心がなくとも、人間の性質の科学に興味があれば、本書の内容を面白がってもらえるのではないかと思う。とはいえ、本書は物語作家向けの本でもある。書き手が必ず直面する問題として、いかに他者の脳の注意をとらえて惹きつけておくか、というものがある。どうすればそれが可能かを少しでも知っておけば、その力を伸ばす助けになるはずだと考えている。これは、物語を読み解くという伝統的な試みとは逆のアプローチだ。典型的な試みには、世界で愛される物語や古くからある神話を比較し、その共通点を探りだすという作業が含まれる。この作業から、連続的な物語事象をレシピのように並べた、あらかじめ形の決まったプロットというものが生まれてくる。なかでももっとも影響力を持つのが、〝冒険への召命〟からスタートし、17のパートからなる英雄の旅を段階的に追跡する、ジョーゼフ・キャンベルの〝原質神話〟であることはまちがいない※5。
このようなプロット構造は、大きな成功をおさめてきた。たくさんの人々を惹きつけ、何十億ドル単位の大きなビジネスとなった。とりわけ映画や長編TVドラマ業界では、ストーリーテリングの産業革命につながった。キャンベルからインスピレーションを得た『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』など、いくつか見事な作品も生まれてはいる。しかし、大半はチョコレートバーのような物語ばかりで、美味しいしもっと食べたくもなるが、結局のところは面白みや深みに欠ける、会議室で作られたみたいな作品なのだ。
伝統的なアプローチの問題点は、構造に目を奪われがちなところだと私は考えている。なぜそうなるかはわかりやすい。〝唯一の真の物語〟、すなわち、どんな物語も評価できる究極の完璧なプロット構造の探求になってしまうからだ。それに、さまざまな動きに切り分けることもなしに、その構造を説明するのは非常に難しい。
現代の物語では、素っ気ない感触を生んでしまう構造を強調しすぎるあまり、損なわれる部分が大きいのではないだろうか。フォーカスを当てるべきはプロットではなく、登場人物ではないかと私は思う。われわれが自然な興味を抱くのは、出来事ではなく人間に対してだ。欠点もあるが魅力的で、その人のために応援し、泣き、クッションに頭突きしたくなるような、特定の個人に対してだ。プロットの表面上の出来事ももちろん重要だし、構造は機能的で規律あるものとして存在しなければならない。しかしそれは、あくまでキャストを支えるためのものだ。
一般的な構造原理や、理解の助けとなる基本的な物語のさまざまな形式はあるにしても、極端に広い範囲の輪郭を超えてまでやるべきことややってはいけないことを規定するのは、おそらくまちがっている。ストーリーテリングの科学の世界に旅してみれば、脳の注意を惹きつけてとらえておくことのできる、たくさんの方法があることがわかってくる。物語の語り手は、さまざまな理由によって進化を遂げてきたたくさんの神経処理に関与し、道徳的な怒り、予期せぬ変化、ステータス・プレー、特異性、好奇心などが、オーケストラの楽器のように演じられるのを待つ。こうしたことを理解すれば、人の心をとらえる深遠で感情的で独創的な物語を、より楽に生みだすことができるようになる。
私はこのアプローチが、より創造的な自由をもたらすことを願っている。ストーリーテリングの科学を理解するメリットのひとつに、一般に与えられている〝ルール〟の裏にある〝なぜ〟を明らかにしてくれるということがある。この知識は力となる。ルールがなぜルールとなったのかを知れば、ルールをどうやって知的かつ巧みに破ることができるかもわかるからだ。
とはいえ、キャンベルが見つけだしたような物語理論など軽視してかまわない、と言いたいわけではない。むしろ逆だ。人気があるストーリーテリング本のなかには、最近ようやく科学的にも解明されたような、物語や人間の性質に関する賢明な洞察を記したものもたくさんある。本書でも、こうした書籍を多数引用している。まして、そこに書かれている優れたプロット設計を無視すべきだなどと主張する気も毛頭ない──むしろそれらは、本書の補完として気軽に使えるものだ。実のところこれは、何を強調するかという問題にすぎない。魅力的でユニークなプロットは、箇条書きのリストからではなく、登場人物から浮かび上がってくるものだと私は考えている。豊かで真実味があり、物語的なサプライズにあふれる登場人物を創造するのにもっとも良い方法は、登場人物が現実の人生においてどのように動くかを見いだすことだ──そしてそれは、科学に目を向けるということでもある。
私は、自分が小説に取り組んでいたときにあればよかったと思うようなストーリーテリング本を書こうと努力してきた。〝やらなければいけないこと〟リストを作って創作のスピリットを殺したりせず、実践的なやり方を示すことによって、この『ストーリーテリングの科学』のバランスをとろうとしてきた。小説家でありクリエイティブ・ライティングの指導者でもあるジョン・ガードナーの、「もっとも美しいとされる絶対的な事象は、圧力下では相対的となる」※6という主張には、私も賛同する。もしあなたがストーリーテリングのプロジェクトに乗りだすつもりなら、ここから先の内容は、義務の羅列ではなく、使うべきか否か、使うならどう使うべきかを自分で選べる武器と考えてもらいたい。また本書の付録では、何年にもわたり私の講座で成功をおさめてきた、実践的なやり方の概略もたどっていこうと思う。この〝神聖なる欠点アプローチ〟は登場人物優先のプロセスで、脳が人生を生みだすさまざまなやり方をまねて物語を創造しようとする試みであり、真実味や新鮮味を感じさせ、潜在的なドラマをあらかじめ仕込んでおくためのものだ。
本書は4章からなり、各章でストーリーテリングの各層を探っていく。最初に、物語の語り手や脳が、いかに自分の内に色あざやかな世界を創造するのかを検討する。次に、その世界の中心にいる、欠点のある主人公について見ていく。そのあと、人間の潜在意識に分け入り、人生を奇妙で厄介なものにする隠れた闘争や意志について解き明かし、それを語る物語がいかに深遠かつ魅力的で、予想のつかない感情的なものとなるかを論じる。最後に、物語の意味や目的を概観し、プロットやエンディングについての新たな見解も紹介したい。
ここからスタートするのは、何世代にもわたる賢明な物語理論家たちの発見を、同じように賢明な科学界の人々の知識と照らし合わせ、筋を通そうとする試みだ。これらすべての人々に、かぎりない感謝を伝えたい。
2018年9月
ウィル・ストー
※1 Evolutionary Psychology, Robin Dunbar, Louise Barrett & John Lycett (Oneworld, 2007) p. 133.
※2 ‘Grandparents: The uniquely designed to Storytellers the Who Bind pass on stories Us; Grandparents may human culture’, be Gopnik, Wall Street Journal, 29 great March of Alison 2018.
※3 The Origins of Creativity, Edward O. Wilson (Liveright, 2017) pp. 22–24.
※4 The Righteous Mind, Jonathan Haidt (Allen Lane, 2012) p. 281.〔ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか──対立を超えるための道徳心理学』高橋洋訳、紀伊國屋書店、2014年〕
※5 The Hero with a Thousand Faces, Joseph Campbell (Fontana, 1993).〔ジョーゼフ・キャンベル『千の顔をもつ英雄〔新訳版〕』上下巻、倉田真木・斎藤静代・関根光宏訳、早川書房、2015年〕
※6 The Art of Fiction, John Gardner (Vintage, 1993) p. 3.
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。