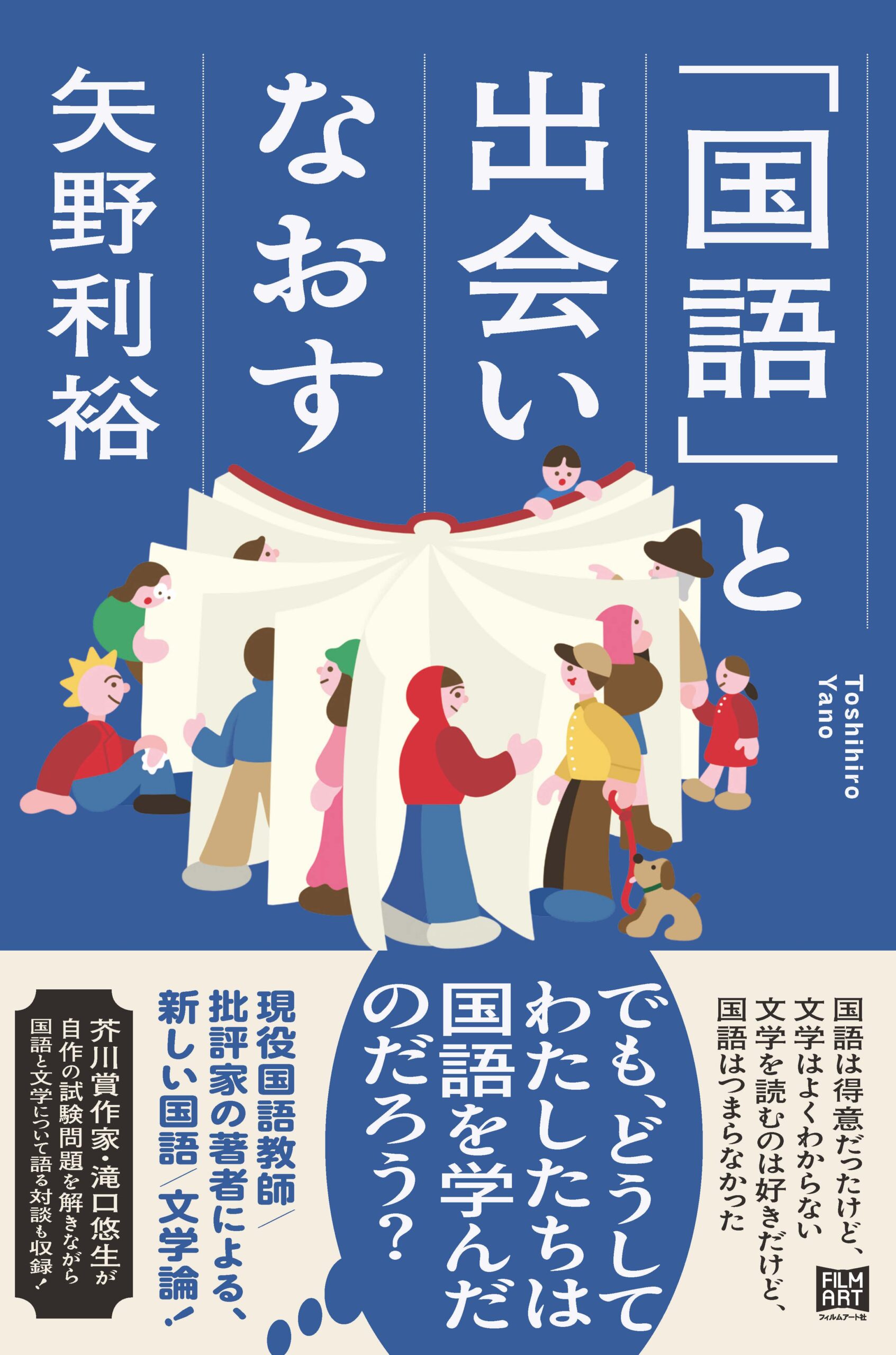矢野利裕『「国語」と出会いなおす』(フィルムアート社)を読む。私は国語、特に現代国語を「簡単なゲーム」と考える人間だったが、それは正に国語が「文芸批評」と足並みを揃えていたからだった。 文庫本の解説を読むとひたすらイデオロギー批評で埋まっていたから、現代国語の場合、実は出題文を精読する必要すらなく解けた。 何故なら「著名作家による出題文ではなく、設問を書いた出題者(教員)の意図、更に言えば党派性を掴んでしまえば正解する」=「出題文ではなく、設問をイデオロギー批評して党派性を把握し、設問者の望んでいる党派性に沿った回答を書けばいい」というのがわかっていたので、出題文は置き去りにして「設問を書いた出題者の党派性による意図を読む」。これは批評家の意図を読むぐらい簡単なことだった。 要は「こいつは右か左か、近代主義者かポストモダンか、美学側か政治側か」を大体見抜けば一発で正解する。小論文もそうで、出題者の党派性に沿った小論文を書けば良い。 「なんて簡単なゲームだ」と思っていて、正直、今の「批評」は未だ国語の「設問」と同じレベルにあるとも思っている。 何故なら相変わらず党派性に満ちているので、イデオロギー批評を「批評」に対して行えば、一発で何を意図しているか結論まで読めてしまう。これが私が「イデオロギー批評ほど簡単な結論ありきなものはないからくだらない」という所以だ。
だが、著者同様「書き過ぎない文章」で書かれている小説は卑怯だと思っていたのも確かだ。 「大抵の批評はひたすら自説を叫ぶ政治活動家のアジビラに似ているし、大抵の小説は政治家の国会答弁に似ている」と思っていた。 だから海外文学やその影響を如実に受けた一部の日本の小説家のように「小説なのに書き尽くす文章」を私は好むし、批評のくせに「どうせ答えは決まってるんだから答えだけ提示しちゃえばいいだろう」と専ら思考の過程ではなく、答えを放りだしてくることに徹する澁澤龍彦(エッセイと謙遜していたが)と、その批判者なのにやはり答えだけの提示を専ら行う浅田彰の文章は好ましく映った。
が、この本の「出題者・矢野利裕」には私が学生時代にやっていたような読みは無効だ。なんてタフな「出題者」なのかと思った。何故なら彼は党派性による読みをいくつも提示するが、どの読みにも与しない。そしてどちらにも頷けるところがあるとするが、どちらにも疑問を提示する。 こうしてしまえばイデオロギー批評で出題者の設問を解くことは困難だ。 国語も私のような賢しい輩が解けないように矢野利裕の批評方法=出題を行うべきだろう。 「批評で書き過ぎない」「小説で書かな過ぎない」文章を出題文とし、設問もそうすべきではないか。 この本は国語教育が結局文芸批評と足並みを揃えていたことを暴露し、文芸批評の悪癖である党派性に与しないことによって、国語教育も文芸批評も再生しようとする=魅力的な出題と設問をしようとしている。 私も学生時代に「出題者・矢野利裕」のような先生に出会いたかった。素晴らしくタフな本だった。