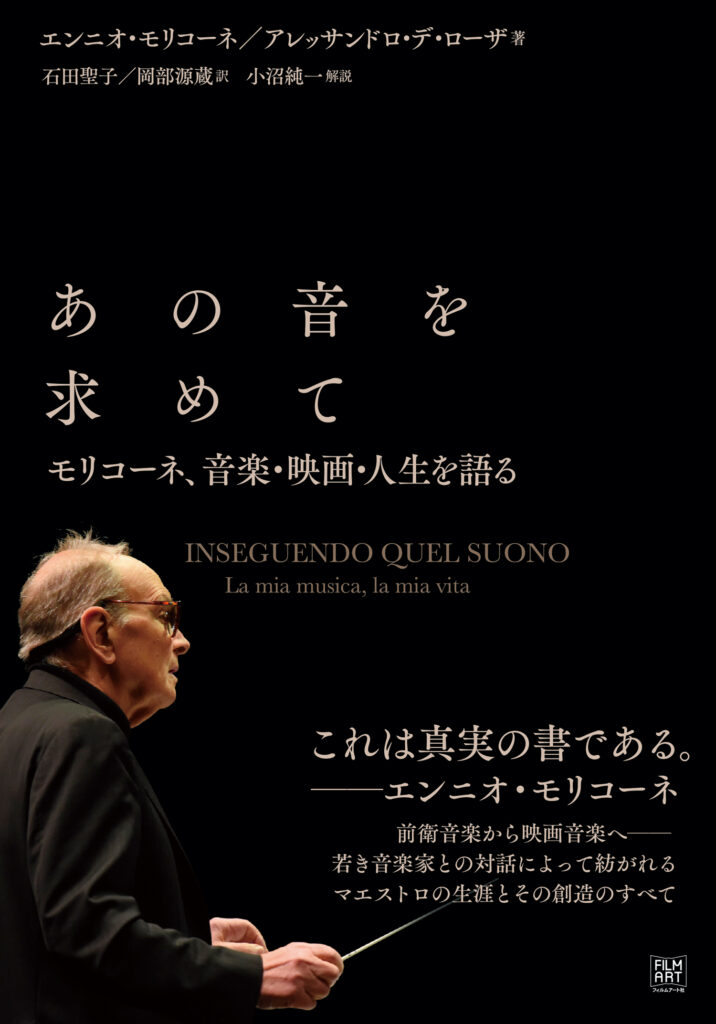セルジオ・レオーネと「ドル箱三部作」
『荒野の用心棒』――神話と現実
――圧倒的で独創的な編曲をもってルチアーノ・サルチェ監督作品で映画デビューを飾ったのが1961年のことでした……が、映画ファンの多くがあなたの存在を意識しだしたのは1964年の『荒野の用心棒』以降でしたね。
セルジオ・レオーネ監督とはどうやって出会ったんですか?
モリコーネ 1963年の暮れに家の電話が鳴った。「もしもし、セルジオ・レオーネと申しますが……」、そう切り出した人物は自分は映画監督で、とにかく自作の企画について詳しい話をするためにすぐにでも会いたいと言ってきたんだ。わたしがモンテヴェルデ・ヴェッキオ地区に住んでる頃のことだった。
レオーネという苗字には聞き覚えがあったんだけど、その人物を玄関先で迎えた瞬間にわたしの脳内で何かが弾けたんだ。何やら見覚えのある下唇の動きにたちまち目が引きつけられた。そう、その男はわたしが小学3年生の頃に知り合った少年にそっくりだったんだ。
わたしは「え、もしかして、小学校のときのレオーネ?」と訊いた。
「ひょっとしてきみってトラステヴェレ通りで一緒だったモリコーネかい?」
信じられなかったよ。
古いクラス写真を見てみると、わたしたち二人がいるじゃないか。30年も経ってから再会するなんて思いもよらなかった。
――『荒野の用心棒』の相談に来たんですか?
モリコーネ そう、ただし当時はまだ『すばらしき流れ者(Il magnifico straniero)』という仮題で呼ばれていたけどね。わたしは西部劇については全然詳しくなかったんだけど、イタリア・スペイン合作でリカルド・ブラスコとマリオ・カイアーノが監督を務めた『赤い砂の決闘』(63)をその前年に担当していて、さらに、『拳銃は問答無用(Le pistole non discutono)』(64)の楽曲を制作している最中だったんだ。
昼から夜にかけて一緒に過ごして、トラステヴェレ地区にあるフィリッポの店に夕食に出かけた。フィリッポは「馬車引き」というあだ名で呼ばれていたわたしたちの小学校時代の同級生で、父親のケッコ氏から譲り受けたおいしい店をやっていたんだ。セルジオが誘ってくれて、勘定ももってくれた。そのあとで、わたしに見せたい映画があると言ってきた。
そこでわたしたちはモンテヴェルデ・ヴェッキオ地区にある小さな映画館に向かった。その日、その映画館では黒澤明の『用心棒』(61)のリバイバル上映がおこなわれていたんだ。
――映画は気に入りましたか?
モリコーネ 全然。でもセルジオは興奮していたよ。求めていたものをあの映画の展開に見出したみたいだった。
新月刀に似た刀の名手が拳銃の男と一戦を交える場面があった。無茶な話なんだけど、まさにその無茶苦茶さがレオーネを捉えたんだ。この対決は、ライフル銃を持ったジャン・マリア・ヴォロンテと拳銃を手にしたクリント・イーストウッドの最後の決闘の場面で再現されていたね。
――「拳銃がライフル銃と対決したら勝ち目がない?」イーストウッドは続けて、「試してみよう」と言います。レオーネ流のロックで大胆不敵な拳銃使いの神髄ここにあり、ですよね。
モリコーネ セルジオは黒澤作品から構成を借り受けて、そこにアイロニーや辛辣さ、大胆不敵さといった要素を付け加えた。舞台をアメリカ西部に移してね。
わたしは自分の役割があのピカレスク風で攻撃的な雰囲気を音楽で盛り立てることにあるとただちに理解したよ。
当時はこの先何が起こるかなんて想像できなかった。セルジオとの最初の出会いとあの日のことはいまだにとてもいい思い出だよ。会った瞬間、面白いやつに違いないと思ったからね。
――レオーネ監督は当初から西部劇を神話の世界として語ろうとしていたように思えます。
モリコーネ 後年、セルジオは史上最大の西部劇の作家はホメーロスであると言うようになった。セルジオはホメーロスの描く英雄の姿に自身の映画のカウボーイたちの原型を見ていたんだ。1964年の時点ですでにそういう考えがあったかはわからないけれど、セルジオが大きな野心を抱いていることはすぐに見て取れた。だって、アメリカ映画のモデルとイタリアのコンメディア・デッラルテ〔16世紀頃に北イタリアで誕生した演劇形態。仮面を使用する即興喜劇〕を接続させることで西部劇を語り直そうとしていたんだからね。その出所を明らかにしながら斬新で先端的に見せつつ、それでいてそのどちらからも距離を保とうとしていた。口で言うのは簡単だけど、実際にやるとなると別の話だよ。
当時、そうしたやり方が有効かどうか疑ったのも事実だ。その頃、イタリアで西部劇は大きな危機に直面していたからね。しかしその後ほんの数年のうちにレオーネは西部劇に新たな息吹を吹き込んでみせた。そのための気概と手腕を兼ね備えた人物は彼以外にはいなかっただろうね。
――その手法に懐疑的だったのはあなた一人だけではありません。ヴォロンテも、不評を買った舞台のせいで抱えた借金のためだけにあの映画に出たのであって、映画が成功するとは思っていなかったとあるインタビューで語っていますから……それに対し、『荒野の用心棒』の成功はすさまじいものでした。黒澤サイドから訴訟を起こされることにもなりました。
モリコーネ 映画を製作したジョリー・フィルムは、黒澤の映画の製作会社に翻案権の支払いを済ませていなかった。それで、訴訟騒ぎが起こった。それにしても、あれほど成功するなんて誰も考えていなかったからね。あんな低予算の映画がイタリアの国外に出るとはね。
レオーネは、「南イタリアのカタンツァーロにまで行けば御の字だが、できる限りのことはやらないとな」なんて言っていたもんだよ。
プロデューサーはより強いインパクトを与えるためにこの映画をアメリカ製として通そうとした。それで、わたしたちは偽名で働くことになったんだ。ラモン役のヴォロンテはジョン・ウェルズ、わたしの名前はダン・サヴィオ─カイアーノ監督作品でも使った名前だ――レオーネはボブ・ロバートソンという具合だ。唯一、実名を使ったのは主人公の名無しの男、映画に出はじめたばかりでほぼ無名のクリント・イーストウッドだった。
――1964年9月12日、『荒野の用心棒』はまずフィレンツェで封切られ、以来、カタンツァーロをはるかに越え、比類ない成功を収めました……制作時の思い出にはどのようなものがありますか?
モリコーネ セルジオとの関係を測る試金石のような作品で、短期間に最高の共同作業から諍いまでありとあらゆることが起こったよ。
ラストシーンをめぐっては喧嘩別れするところだった。セルジオが編集の段階で暫定的に使用した曲に固執したからね。それはディミトリ・ティオムキン作曲の《皆殺しの歌》という曲で、ハワード・ホークスが監督し、ジョン・ウェインとディーン・マーティンが出演した『リオ・ブラボー』(59)で使われたものだった。実際、こうしたことはよくあったし、今でもよくある。編集の段階でオリジナル曲がまだ書かれていない場合、既存の楽曲を使って間に合わせるんだ。
そうすると、監督はその曲に馴染んでしまって、考えをあらためさせたり新しいものに注意を差し向けたりするのは難しくなる。セルジオの場合も同じだった。《皆殺しの歌》に入れ込み、それを使いたがったんだ。
――それでどうしたんですか?
モリコーネ 「もしそれを使うなら、この仕事を降りる」と言って、レオーネを突き放してやった(1963年はまったくお金のない年だったのに!)。
レオーネはまもなく歩み寄ってくれて、困惑しつつも最大限の自由を与えてくれた。「エンニオ、真似しろとは言わんが似た感じで頼む……」ってね。
いったい何が言いたかったんだろうね。いずれにせよ、わたしはそのシーンが彼にとって意味するものから抜け出すことができずにいた。つまり、セルジオによればメキシコとアメリカの伝統が入り混じっているという南部テキサスの雰囲気に相応しい死の舞のイメージにね。
これに反発してやろうと、その二年前にユージン・オニールの『海洋劇(I drammi marini)』のために作曲した子守歌をこっそり紛れ込ませてやった。決闘に向けていやましに高まってゆくトランペットの重厚感を引き立てるような明快なトーンのアレンジを施した。それをピアノで弾いて聴かせると、レオーネは納得したようだった〔譜例2‐3〕。
「いいね、とてもいい……でも、《皆殺しの歌》の響きがないとな」
「大丈夫だって。ミケーレ・ラチェレンツァに聴いてもらえばいい」、そう言って彼をなだめたよ。
そこでわたしたちは再び衝突することになった。レオーネはトランペット奏者にニニ・ロッソを望んでいた。当時、トランペットとヴォーカルを興味深くミックスさせたいくつかの楽曲で大当たりして名を馳せていた人物だ。一方のわたしはというと、音楽院で一緒だった優れたトランペット奏者のラチェレンツァを推していた。この役には彼のほうがふさわしいことははっきりしていたからね。ロッソはRCAと契約を交わしていなかったばかりか、当時とても忙しくしていた。それで結局、わたしの案が通ったんだ。
ミケーレは、依頼したとおりメキシコ風で勇ましい調子を付与するべくわたしが書いたメリスマと装飾音を一つ残らず演奏したばかりか、それ以上のものをもたらしてくれた。最後の収録では、レオーネに望まれていないのを知って、目に涙を溜めて演奏していたよ。わたしは彼にこう声をかけてやった。「落ち着いて。もっと軍隊風に、もっとメキシコ風に吹いてみて。わたしが書いたメリスマに身を任せて、自由にやったらいい」ってね。
そしてこの曲は《荒野の用心棒》と名づけられ、映画のメインテーマになったんだ。
――以前書いた楽曲を使ったことをレオーネ監督に打ち明けたことは?
モリコーネ あるよ。ただ、何年も経ってからね。以来、セルジオはわたしのボツ曲を残らず聴きたがるようになった。その後、そのなかの何曲かを使ったこともあるよ。
――オープニングクレジットのときに流れる曲のなかでコーラスが「風と炎(wind and fire)」と歌っているのはどうしてですか?
モリコーネ 1962年にRCAのために、ウディ・ガスリーの《みのりの牧場(Pastures of Plenty)》をピーター・テーヴィス用にアレンジする仕事をしていたんだ。テーヴィスは、カリフォルニア出身でイタリアでもよく仕事をしていた優れた歌手だ。
編曲に取り組んでいるとき、鞭や口笛の音を挿入することでガスリーが思い描いた彼方の地と聴衆を結びつけようと考えた。一方、鐘の音を使って、その日常からかけ離れた都会で暮らしたいと願う田舎の人間を描こうとしたんだ。元の歌の旋律からは大きく乖離したものとなった編曲版のコーラスには「塵とともに来たりて、風とともに去る(We come with the dust and we’re gone with the wind)」という歌詞の終わりの部分を採用した。
レオーネにこの曲を聴いてもらったときに背景にある概念の説明をすると、すばらしい楽曲だと言って、コーラスも含めた全体をそのまま用いるよう求めてきたんだ。わたしは土台の部分を抜き出して、それに合わせて新しいメロディを書いた。それが、アレッサンドロ・アレッサンドローニの口笛にはじまり、次いで、ブルーノ・バッティスティ・ダマーリオがエレキギターで演奏する箇所だ〔譜例2‐4〕。
さらに、コーラスのブリッジの部分もそのまま流用することにしたんだけど、せめて歌詞に少し手を加えたいと思った。それで、「風とともに(with the wind)」だったのを「風と炎(wind and fire)」に変えたというわけなんだ。
――この曲に用いられている音色のうち、口笛がいちばん原始的ながら内面的でもあります。ぱっとしない日々を送っている人間にとって、夜に火のそばで口笛を吹きならすのは、誇りとささやかな不遜をもって孤独を遠ざける唯一の方法です。
モリコーネ アレッサンドローニの口笛があまりに効果的だったので、セルジオは『夕陽のガンマン』(65)のオープニングにも前作のオープニングで使ったのと同じ曲を使おうと考えたんだ。そのことにかなりこだわっていたけれど、幸いにも、同じ雰囲気を引き継ぎながらやや変化をつけて改良した曲を選んでもらうことができたよ。
――アレッサンドローニの口笛がダマーリオのエレキギターに取って代わる。これもまた非常に特徴的な音色です。シャドウズの曲調に結びつけられることもあります。
モリコーネ 当時、そのバンドについて耳にしたことはなかった。もともと編曲するのにエレキギターを使いはじめて、パオロ・カヴァーラ監督のドキュメンタリー映画『ゼロの世代』(64)でも使ったんだ。エレキベースはまだなかったから、代わりに四弦バスギターが使われていて、わたしもそれを使うことにした。
『荒野の用心棒』が封切られたとき、斬新だと騒がれたけれど、実際にはエレキギターは何年も前から使っていた。ただ、ソロの楽器としてではなくね。エレキギターの硬質で鋭い音は映画の雰囲気にぴったりだと思ったよ。
――アレッサンドローニは、クリストファー・フレイリングのインタビューで、録音スタジオではレオーネ監督のことが恐ろしくて縮み上がっていたとおどけて語っています。監督は肩をぼんっと叩いては「おい、今日はいちばん上等な口笛を吹くんだぞ。いいな」と言ってきたんだそうです。
モリコーネ セルジオの口笛は強烈だからなあ……(微笑む)。収録のときにはしょっちゅうスタジオに顔を出していたよ。細かなことを気にする男だから、当初からの信頼関係にもかかわらず、出来栄えをチェックしたがった。あるいは単に遊びに来たりね。
一度、楽曲の収録にレオーネと一緒に立ち会ったときにあまり順調にいかないことがあった。レオーネはいつも以上に苛立っていて、あるシークエンス用に切れのいいクレッシェンドを求めていた。わたしは指揮をしていたから彼と話をしてなだめることができなかった。すると突然、ミキサー上のスタジオ内との連絡回線をオンにするトークバック・キーを叩くと、団員たちに向かって何やらがなり立てたんだ。それに対して、第一ヴァイオリン奏者のフランコ・タンポーニは、わたしとはほぼいつも一緒に仕事をしてきた優れた人物で音楽家なんだけど、すっと立ち上がると威厳を湛えた落ち着き払った口調で丁寧に「お言葉ですが、この場ではモリコーネ氏の指示にのみ従わせていただきます」と言った。こういう意味で、セルジオは抑えの利かない男だったよ。
この一件の直後、すっかり意気消沈したレオーネがこう言ってきた。「あのさ、楽曲の指揮は誰か別の人に任せて、きみはわたしと一緒にミキサー室にいたらどうかな? そのほうがコミュニケーションがとりやすいし、団員にも効果的な方法で指示が出せるだろうし……」。実際に、音を前後にずらしたり演奏方法を変更する必要は頻繁に生じるから、他の誰かに指揮を任せて自分は監督のそばにいたほうが、楽器や音色の選択、譜面、作曲家のアイデア、映画のイメージや監督の意向といったものをしっかり結び合わせることができるんだ。
それは名案だと思い、実際にその直後から、他の映画監督との仕事の際にもそうするのが習慣になった。指揮には友人であり偉大な音楽家のブルーノ・ニコライを迎えて、1974年までほぼすべてのわたしの曲を指揮してもらったよ。
――『荒野の用心棒』の音楽でナストロ・ダルジェント賞を受賞し、同年のイタリアにおける興行収入ランキングの「サウンドトラック」部門で一位に輝きました。
モリコーネ 率直に言うとね、得られた賛意とは裏腹に、いまでもこの映画の音楽はわたしが映画用に手がけた楽曲中最悪の出来だったと思っているよ。その翌年、大ヒットのためまだロードショー中だったこの映画をレオーネと一緒にクイリナーレ座に観に行ったことがあるんだけど、終演後、外に出たわたしたちは顔を見合わせて一瞬黙り込んでからほぼ同時に言ったんだ。「ひっどい映画だな!」って。二人でげらげら笑って、家路についた。考えさせられる一件だったよ。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。